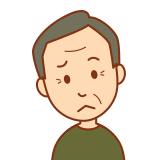
最近、子どもとの人間関係に悩んでいて…
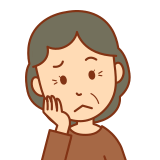
私は職場の人間関係でストレスを感じることが多いわ…
今や、かなりのストレスフルである学校現場。
今日は学校現場がストレスフルである原因とその対処法をまとめます。
私は大学卒業と同時に教員になり、今年で10年目を迎えました。
色々な学校、色々な子どもたちに出会ってこれまで勤務してきました。
その中でかなり悩んだり、病んだりすることもありました。
今では生徒指導主任をはじめ、学校運営に携わる大きな分掌の主任を任されることも多くなってきましたが、ずいぶんストレスなく働くことができています。
それは、私が「ストレスなく働けるメンタルを作ってこれたから」です。
様々な対処法がまとめられた記事や書籍はありますが、今回は私が最も参考にしているTeststeroneさんの書籍をもとにストレスへの対処法を紹介します。

教員のストレスの原因とは
まずは、学校の先生の「ストレスの原因」を明らかにしていきましょう。
教員のストレスに関する資料として「過労死等防止対策白書」があります。
この資料には、教員のストレスに影響を与える上位3項目が以下のように報告されています。
・長時間勤務の多さ
・職場の人間関係
・保護者、子供を取り巻く環境やその対応
長時間勤務の多さについて
文科省から出されている「教員勤務実態調査」によると、小学校教員の平日における平均勤務時間は「11時間15分」とされています。
「平均勤務時間」ですから、12時間以上働く先生が多くいることも容易に想像できるでしょう。
これは法定労働時間の1日8時間をはるかに上回り、さらに1日12時間労働といった「過労死ライン」にも近づいています。
いかに、教員の長時間労働が深刻であるかがわかるかと思います。
しかし、ただ「長時間労働」そのものが問題なのではありません。
それによって自分自身の時間を確保することができない、突発的な業務が多くあり、本来の授業準備や学級経営に時間をかけられないなどといったように、長時間労働が仕事や生活に支障をきたしている状況にストレスを抱えている教員が多いのが実態です。
職場の人間関係について
次は教員同士の人間関係についてです。
学校は閉ざされたコミュニティーです。
コミュニケーションをとる相手が長時間、学校内の教員同士に限られているという、ある意味特殊な仕事現場です。
外部の人とつながることはほとんどありません。
お客や取引先の相手が常に眼前にある企業と違い、努力せずとも子どもたちは変わらず登校してくれる学校現場。
そのため、教員が常に気にして生活していかなければならないのは、同僚である先生たちです。
そのコミュニティーの中で人間関係を構築しなければならないため、教員同士の関係やお互いの評価の固定化から、一度関係がこじれたらなかなか修復できないという実態があります。
そのような中で、常に気を張り、気を使いながら毎日生きている先生たちが多く、かなりのストレスを抱えていることが想像できます。
保護者、子供を取り巻く環境やその対応
本来、教育の良きパートナーとして子どもたちの成長を支え合っていくはずの保護者。
しかし、その保護者は立場や教育観の違いなどから教員の仕事に大きな壁となって立ちはだかってしまっていることも現実です。
保護者からの怒りの感情をぶつけられたり、対応が難しい方がおられることもあり、そしてそれによって仕事が一気に複雑化することもあって、休職や離職につながってしまほどにストレスを感じる教員が多いことも事実です。
また、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。
いじめや学級崩壊というこれまでに何度も問題になってきた事象はいまだに学校現場に強く根ざしています。
さらに、不登校や喫煙、万引き、自傷行為などといった問題行動、さらに児童虐待やネグレクトといった家庭問題も見受けられるようになっており、それらに対応する教員のストレスはかなり大きなものになっています。
教員にのしかかるさらなる仕事とは
それらのストレスフルな状況に加え、今や学校現場は「個にスポット」を当てた指導がより一層求められています。
「ユニバーサルデザイン」「インクルーシブ教育」「個別の指導計画」「個人内評価」など、これまで以上に「個性に寄り添った教育」が求められているのが現状です。
このような状況下で、教員1人ではとても対応しきれない事例も往々にして存在します。
責任感や熱意のある先生が子どもたちの役に立てていないと感じ、自信をなくしたり、緊張や不安で疲弊しきってしまう例も多くみられます。
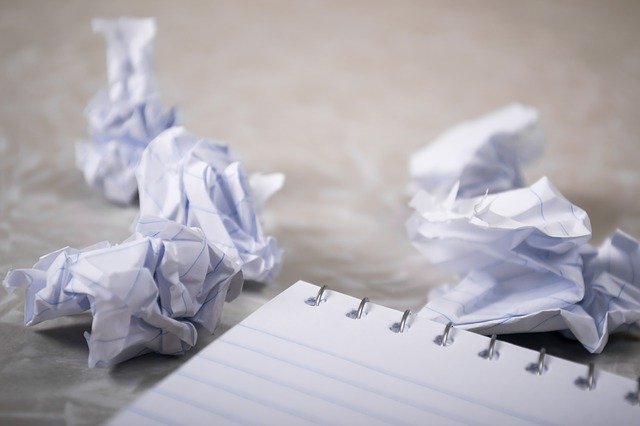
そんな学校現場でストレスをなくす具体的な対処法
今まで、学校現場の過酷な状況を紹介してきました。
そのような状況を知って絶望された方もおられるかもしれません。
しかし、私はそのような中でもずいぶんストレスなく生きられるようになって来ました。
それは「考え方」が変わったからです。
私が強くなったわけでも、それらの状況にうまく対応できる指導力を身につけたわけでもありません。
今回紹介する「考え方」を知り、意識するだけでも多くの方が少し楽に働けるのではないかと思っています。
【対策1】コントロールできないことで悩むのをやめる
自然災害や天候など、自分の思いでどうこうできないことってありますよね。
それと同様に、保護者や教員同士の声や評価、どんな子供と出会い、どんな教員集団で働くことになるのか、といったことも自分にコントロールできることではありません。
こういった「自分にコントロールできないことで悩むのをやめる」ときっぱり意識することが大切です。
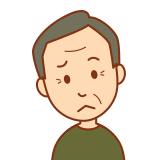
じゃあ、そういうことで悩んでしまったらどうしたらいいの?
答えは明確です。
「諦める」です。
でも、この「諦め」はネガティブな諦めではなく、極めて「ポジティブな諦め」であると意識することが大切です。
つまり、「自分にコントロールできることのみに集中する」という覚悟を決めるわけです。
保護者を変えることも、子どもを変えることも、先生集団を変えることも不可能です。
どんな人に巡り合ったとしても、「自分にできることだけ」に集中できるので、ストレスを抱えることがなくなります。
【対策2】心配するのをやめる
「心配」とは、未来のことやまだ分からないことに対して「不安」になっている状態のことを指します。
・こんなことを指導したらまた保護者が何か言ってくるかも
・この提案文書であの人は納得してくれないかもしれない
・職員同士の関係が悪くて、自分にもよくない影響があるかもしれない
そんな「もしかしたら」という自分の想像の世界で自分を苦しめる行為、それが「心配する」ということです。
Teststeroneさんは「心配する」ということに対して、こうも述べています。
「心配するということは、「自分の時間」を減らし、「心理的ダメージ」を自らに与える愚かな行いである」
『ストレスゼロの生き方』より
まだ起こっていない不確実なことで自分を不安定にさせるのはやめましょう。
そして、確かなことに力を集中させ、成果をあげましょう。
【対策3】愚痴を捨てる
「愚痴を言う」という行為は「もっとも手軽なストレス解消法」でありながら、「もっとも危険なストレス解消法」でもあります。
なぜなら、愚痴を言うと
・周りに愚痴を言う人が集まる
・愚痴を言うことで満足してしまい、前進しない
からです。
でも、少しは愚痴を言いたくなることもあるかもしれませんよね。
そんな時は、
・では、どうすればいい状況になるかな?
・どうすれば、もっと成果をあげられそうかな?
と、改善策や自分とセットで考えるようにしましょう。
そうすることで、ただの愚痴ではなく、次に向けての貴重なエネルギーにもなります。
【対策+1】本当に辛い時は逃げる
ストレスゼロを目指して、3点ポイントを書いてきました。
でも、本当に追い込まれてしまう時、どうしようもない時ってやっぱりあります。
自分の手におえない状況になってしまうこともあるでしょう。
そんな時は逃げてしまいましょう。遠慮なくその場から逃げてしまうことが大切です。
・あの先生も頑張っているから私も…
・私がやめたらみんなに迷惑がかかる
・自分だけ逃げるのはなんだか申し訳ない…
そんなことを言っていられる状況ではない時もあります。
Teststeroneさんもこれは「提案」ではなく「命令だ」と言っています。
自分の痛覚が残っている時はチャンスです。
それさえも麻痺してしまうと、どうしようもありません。
1度きりしかないあなたの人生です。
自分の心身を痛めつけてまで頑張る必要があることなど1つもないはずです。
あなたが元気でいてこそ、教育ができます。
まずは、自分のストレスと正しく向き合って豊かに生きて欲しいと思います。
私自身も今まで書いて来たことを忘れず、幸せを目指して生きたいと思います。
共に頑張りましょう。


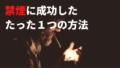
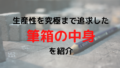
コメント