
「非認知能力」って最近よく聞くけど、どうやったら高められるのかなl…

子育てって何を大事にしたらいいのか分からないなぁ…
色々な場面で聞くようになった「非認知能力」という言葉。
学習指導要領にも、今までの「知識・技能」だけでなく、「学びに向かう人間性」といった点数では測れない項目が追加されました。
これは、今の時代を生き抜く子どもたちを育てる上で、「非認知能力を高めることが必要である」というメッセージでもあります。
でも、どうすれば家庭や学校で「非認知能力」が高められるか、具体的に明記されている書籍や記事にはなかなか巡り会うことができません。
そこで、今回紹介するのが、榎本博明さんの著書『伸びる子どもは◯◯がすごい』です。
著者の長年の経験と海外の研究、現場のさまざまな声を取り入られた本書は「非認知能力」を高めるためのバイブルと言えるでしょう。
本記事を読んで、子どもの教育の質をさらにレベルアップさせましょう。
そして、「伸びる子ども」を育てていきましょう!

そもそも非認知能力とは
「非認知能力」は「認知能力」と比較して定義されています。
認知能力はIQ(知能指数)に代表されるような、点数などで数値化できる知的能力のことをいいます。
IQという言葉は一般的にもよく知られており、その他にはテストの点数など、大人が子どもの能力を把握する上で参考にしやすい指標のひとつです。
それに対して「非認知能力」とは、認知能力以外の能力を広く示す言葉です。
テストなどで数値化することが難しい内面的なスキルの全般を指しており、具体的には「目標を決めて取り組む」「意欲を見せる」「新しい発想をする」「周りの人と円滑なコミュニケーションをとる」などの力のことを指します。
認知能力はもちろん、この非認知能力は「子どもが人生を豊かにする上でとても大切な能力である」と言えます。

多く見られる現代の子ども像とは
現代を生きる子どもたちについて、本書に数多く書かれており、実際に学校現場で働いている私も日々、感じていることがあります。
それはまさに現代の子ども像といえます。
- 傷つきやすい
- すぐに落ち込む
- すぐに反発する
- 感情的になりやすい
- 失敗を過度に恐れる
- 頑張れない
- 粘れない
- 注意や叱責に耐えられない
日々、子どもに接している大人の皆様であれば、思い浮かんでくる顔があるでしょう。
これらの特徴を持った子どもたちが大きくなった時、自らの人生を自らの足で力強く歩んでいくことができるでしょうか。
答えは明らかですよね。Noです。
それでは、このような特徴を持つ子どもたちが多くなっているのはなぜでしょうか。
それも自ずと、答えが出てくるはずです。
現代の子どもを育てているのは、まぎれもなく現代の大人たちなのです。

子どもを取り巻く現代の大人像とは
昨今の教育ブームや社会の変化により、大人の教育感も大いに変化してきました。
- 子どもが傷つかないように気を遣う
- 褒めて育てる教育、叱らない教育
- 大人に気持ちの余裕がなく、すぐに手出し、口出しをする
残業や長時間労働などによって、忙しい毎日を送っている上に、核家族化が進み、自分達だけで子どもの身支度から送り迎え、食事の準備やお風呂など、子育ての全てを行わなければなりません。
そんな大人がゆっくり落ち着いて子どもに接する余裕などどこにもないわけです。
「子どもがじっくり考える時間が大事」「失敗を繰り返しながら成長させる」と頭では分かっていても、ついすぐに答えを言ったり、手伝ったりしてしまうわけです。
コスパが良い商品を求めるのと同様に、子育てにも「コスパ」を求めてしまっている現状があるわけです。
子育てや教育は惜しみなく手をかけるべきであり、コスパを求めるものではありません。
また、「褒めて育てる」「叱らずに育てる」というと聞こえは良いですが、これらは
ということを今一度、確認し直しておく必要がありそうです。
以上のような現状から、甘い子育てが横行し、子どもたちの非認知能力が高まらない原因となっているわけです。
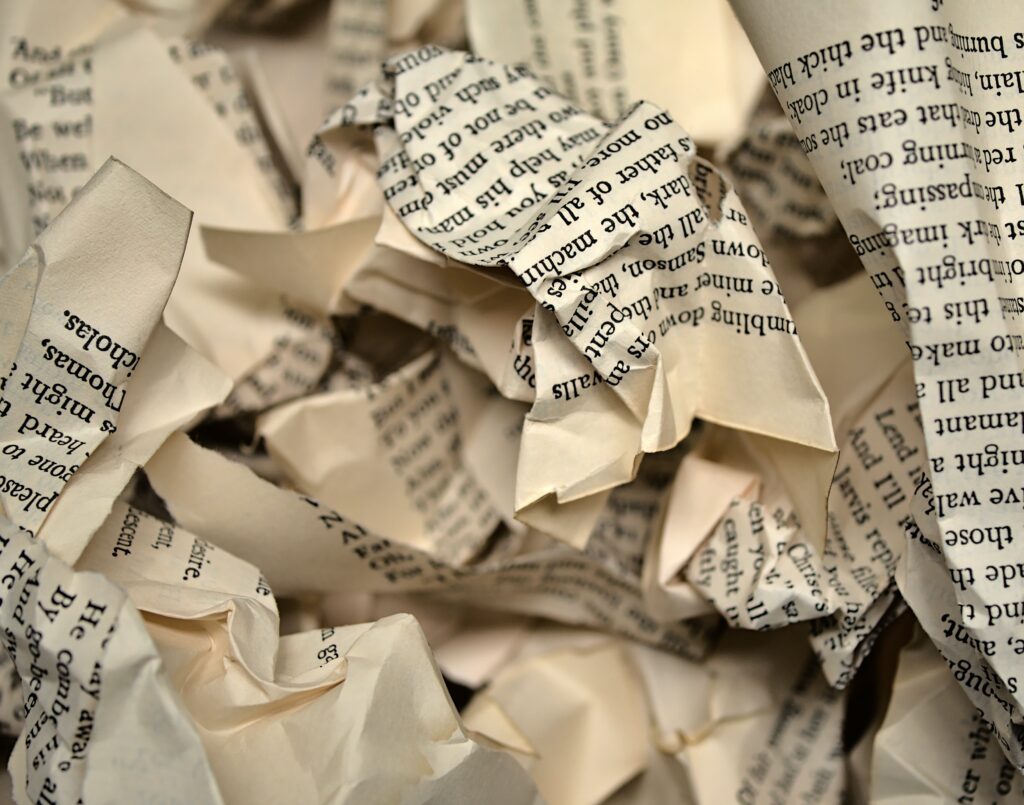
子どもにつけて欲しい力とは
それでは、子どもたちに身につけさせたい力とはどんな力でしょうか。
それは知能指数(IQ)と比較し、心の知能指数(EQ)と言われたりもします。
具体的な例をあげると、
- 挫折状況をなんとか耐え抜く精神力
- 多少苦手なことでもできる限り頑張ってみる意欲
- できないことをくよくよ気にするより気分転換してできることに全力を傾けられる楽観性
- 好きなことや興味のあることに我を忘れて没頭できる集中力
- 必要に応じて感情表現を抑制するなどの衝動をコントロールする力
これら、EQといわれる「自分の生きる道を力強く切り開いていける自発性や忍耐力」を身につけさせることが我々大人の大きな使命であると言えます。

では、どうしたら我が子にEQをつけてあげられるのかしら?

具体的なEQの高め方を解説していくよ!!

非認知能力(EQ)を高めるためにできること選
本書のタイトル『伸びる子どもは◯◯がすごい』の◯◯に入る言葉を考えてみました。
インターネット上の本書のレビューにもさまざまな意見が載せられています。
私が思う◯◯に入る言葉は「親の非認知能力」です。
伸びる子どもは「親の非認知能力」がすごい!
私も本書を読む前は、子ども自身の「非認知能力」や「レジリエンス」などの言葉が入るのだと思っていました。
しかし、今、子どもを育てる親の「非認知能力」こそが大切なのではないかと思っています。
本書でもこのような一節があります。
特に大切なのは大人の非認知能力を高めることです。
子どもは身近な人物や憧れる自分の口癖や仕草、生き方を自然に真似します。これをモデリングといい、親はもっとも身近なモデルであるといえます。
まず親自身が感情コントロール力を身につける必要があります。
これは、なんとなく分かっていたものの、こうはっきり書かれると、背筋がピンと伸びる思いがしますよね。
では、子どもの良きモデル、良き教育者になるための具体的なポイントを解説していきましょう。
親が感情コントロールをする
適切に感情コントロールできている親の元で育つと、子ども自身も適切な感情コントロールができるよになります。
もちろん、その反対も然りです。
- 親が怒りを爆発させていないか
- 嘆き悲しんでいないか
- 感情に溺れていないか
- 衝動的に怒りを爆発させていないか
親である自分自身の感情コントロールに気をつけましょう。
親が粘り強く何かに夢中になる
子どもに「粘り強く取り組む力」をつけさせる前に、親である自分自身が何かに粘り強く取り組んでいるか振り返ってみる必要がありそうです。
- 何かに夢中になって取り組めているか
- 忍耐力、頑張る力はあるか
- すぐに飽きたり、嫌になったりして途中で投げ出していないか
- 今、自分は頑張っているか
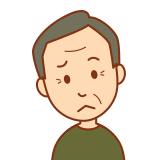
毎日、忙しいのに何かを頑張るなんて難しいよ〜
そんな声が聞こえてきそうですが、子どもを育てている今だからこそ、私たち自身も熱中できる何かを探しませんか?
- ランニングを始める
- 1週間に1冊を目標に読書をしてみる
- 寝る前に日記を書いてみる
- キャンプを始めてみる
本当に小さなことからでもOKです。
失敗したり、悩んだりしながら頑張る姿を子どもに見せましょう!
親が人の気持ちに寄り添う
子どもに「人の気持ちを大切にしよう」と説く前に、まずは親である自分自身が人の気持ちを大切にした言動ができているか振り返りましょう。
- 人の気持ちに寄り添えているか
- 人の気持ちに常に関心を向けているか
- 人の気持ちに鈍感になっていないか
子どもに簡単に見せられる親の模範となる姿は「ありがとう」を伝えることです。
- 子どもに「ありがとう」を伝える
- パートナーに「ありがとう」を伝える
- 自分の親に「ありがとう」を伝える
- 店員さんに「ありがとう」を伝える
- ご近所さんに「ありがとう」を伝える
自分自身が誰かへの「ありがとう」を見つけ、それを言葉にして伝えるなど、人の気持ちに寄り添った言動ができるようにしましょう。
親が前向きな言葉を発する
子どもは親の姿をモデルとして成長します。
諦めず、前向きな子どもに育って欲しければ、親自身が前向きに生き、前向きな言葉を発することが大切です。
- もうだめだ…
- いやだ、やりたくない
- あぁ、めんどくさい
そんな悲観的な言葉を発する親を見て育つ子どもは同じように悲観的な子どもに育ちます。
- よし、がんばろう!
- 楽しみだ!がんばってみよう!
- 諦めずにやることが大切だからね!
- 挑戦するってワクワクするね!
親自身の言葉を前向きなものに変えていきましょう。
子どももきっと前向きになっていくはずです。
子どもにダメなことはダメ!とはっきり伝える
「褒めて育てる教育」「叱らない子育て」がブームとなり、「子どもを叱る」ことがタブーのように捉えられていることがあります。
傷つけないようにと配慮することで、傷つきやすい子供を育てる
これは本書でも強調して書かれていることの一つです。
大きくなってから、一回一回深く傷つき、立ち直れずにいたら厳しい現実を生きていくことなど、到底不可能です。
そのために、大切なことがあります。それが、
- 小さな失敗やなかなか想い通りにならない苦しい状況を繰り返し経験する
- 失敗による感情的な落ち込みになれる
- 思い通りにならない状況への耐性を高める
ということです。
失敗やわがまま、規則違反が通用しないことを毅然と示す中で心は鍛えられていきます。
今、求められているのは「傷つけない子育て」でなく「傷つきにくい心に育てる子育て」です。
毅然とした親の気持ちを伝えつつ、温かく子どもを見守りましょう。
しかし、失敗させっぱなしでは子どもは立ち直ることができず、本当に心が折れてしまいます。
そんな時は、先ほどもあったように「前向きで」「温かい」言葉をかけ続けましょう。
- 誰だって失敗はするよ
- 挫折することで強くなっていくんだよ
- 結果が全てじゃない、がんばることで力がつくんだ
- 頑張った時の爽快感はかけがえのないものだよ
最後は子どもが自分の足で一歩ずつ進んでいきます。
温かく、最後まで子どもを見守りましょう。

【まとめ】大人の行動をふり返り、子どもの非認知能力を高めよう
子どもの「非認知能力」の高め方を知りたいと思ってご覧になった皆さんには拍子抜けするまとめになっているかもしれません。
子どもの非認知能力を高めるためには親の非認知能力が最も大事
これが結論です。
具体的には
- 親が感情コントロールをする
- 親が粘り強く何かに取り組む
- 親が人の気持ちに寄り添う
- 親が前向きな言葉を発する
- 子どもにダメなことははっきりと伝える
これらの親である我々の生き方を前向きに変えていくことこそが、伸びる子どもを育てることにつながります。
子どもの明るい未来に向けて、今から少しずつ大人の行動を変えてきましょう。
本書にはまだまだたくさんの子育てについてのポイントも書かれています。
気になる方はぜひ、以下からチェックしてみてくださいね!
それではまたっ!!
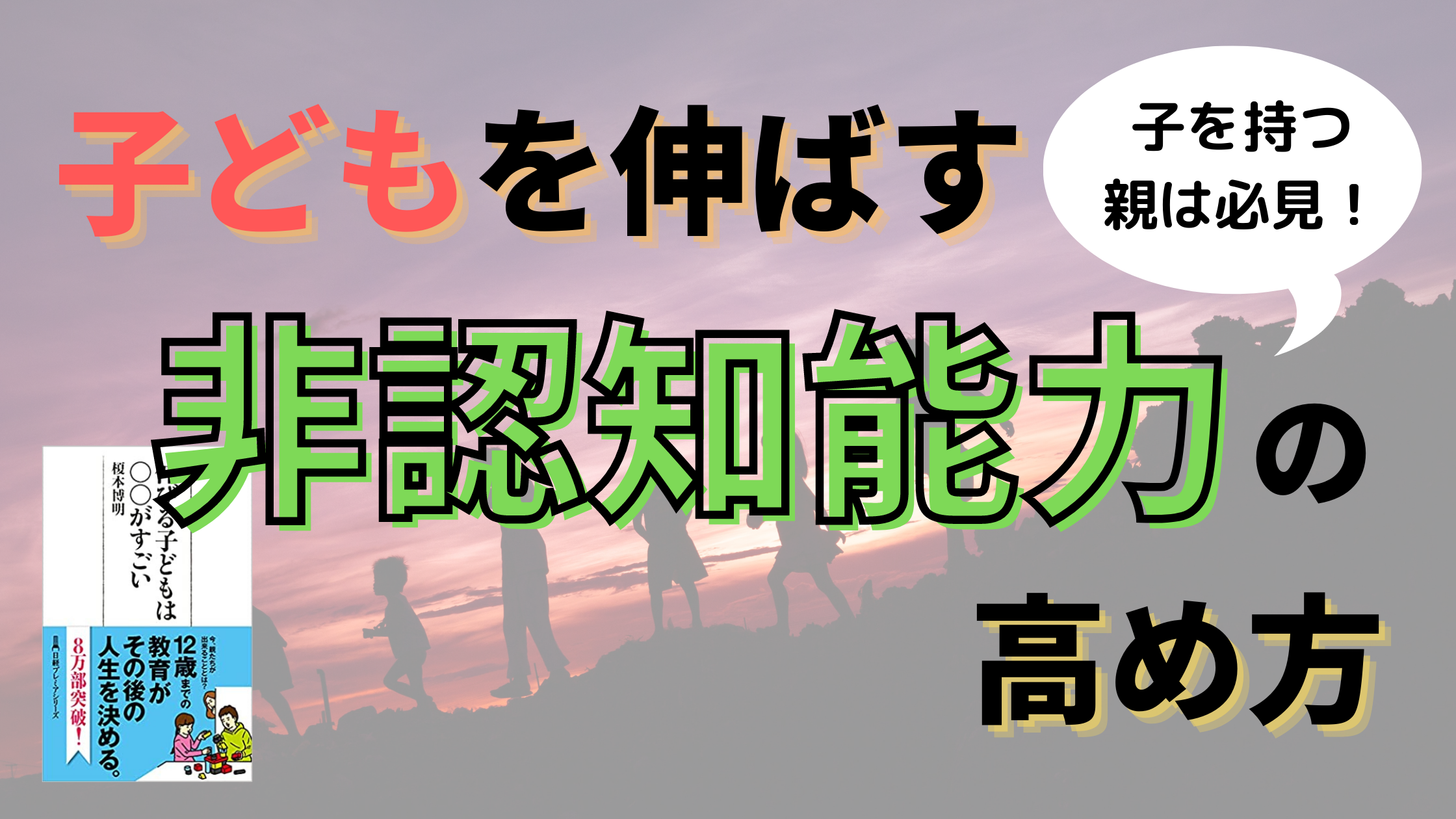
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f18f2e.813fb7a4.19f18f2f.628ecff6/?me_id=1213310&item_id=19786830&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4123%2F9784532264123_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

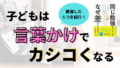
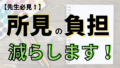
コメント