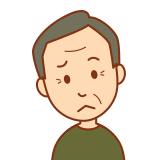
なんで同じ指導をしているのに賢い子とそうでない子がいるんだろう…
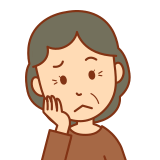
うちの子も、塾に通っているのになかなか賢くならなくて…
「どうやったら賢い子に育てられるんだろう」
これって親や教師をしていると、幾度となく感じ、悩むことの一つではないでしょうか。
- たくさん本を読ませる
- 塾に通わせる
- ドリルを徹底的に取り組ませる
様々な方法を試すけど、いまいち効果を感じられない。
そんな人も多いと思います。
実は、そんな「賢い子」に育てるためには「言葉かけ」がとても大事であることをご存知でしたか?

賢い子に育てるための「言葉かけ」について解説していくよ!
今回は石田勝紀さんの著書『同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?』からエッセンスをまとめて紹介します!

そもそも学びには「3タイプ」ある
そもそもなぜ、子どもたちには学力の差が出てくるのだと思いますか?
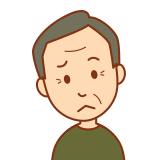
幼少期からの学びの差があるからではないのかな?
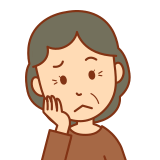
家庭環境?遺伝もあるかしら??
実は、学びのタイプが違うからなんです。
人には3つの学びのタイプがあると言われています。
- 学んでいるように見えるが学ぼうと思っていない子
- 授業中しか学ばない子
- 寝ている時以外、全ての時間で学んでいる子
「あ〜、私はこのタイプだったなぁ」
「あの子はこのタイプかなぁ」などと思い浮かぶ子がいるのではないでしょうか。
もちろん、これを読んでくださったあなたが目指していく子育て、教育は「3 寝ている時以外、全ての時間で学んでいる子」を育てていくことです。
では、どうすれば「寝ている時以外、全ての時間で学んでいる子」を育てられるのでしょうか。
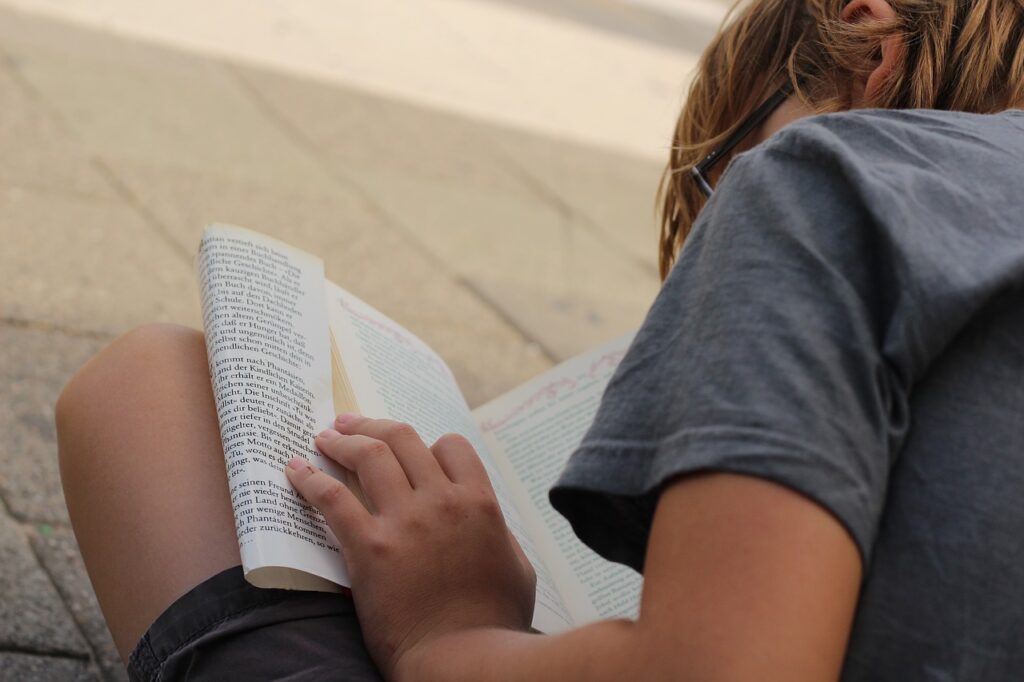
考える力を育てるための声かけ5選
子どもたちの学びの力を高めるためのポイントはたった1つです。
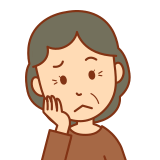
どうすれば「考えている状態」をつくることができるの?
そこで大切なのが「考えさせるための声かけ」を行うことなんです。
大きく分けて「声かけ」には2種類あります。
- 疑問を持たせる声かけ
- まとめさせる声かけ
この2種類の声かけを日常的に行うことで、子どもたちの「考える力」は少しずつ高まっていきます。

お待たせしました!!ではここから具体的な声かけを紹介していくよ!
疑問を持たせる声かけ
①なぜだろう?
「なんでだろうね?」と理由を問うことを習慣にしましょう。
「何?」「どこ?」などの質問は一問一答形式になり、考える必要がありません。
人は「なぜ?」と理由を問われることで、脳のシナプスに電気信号が走ると言われています。
「理由」を問うことで、頭脳が動き出す
- 人に問えば、考える力を高めることができる
- 自分に問えば、自律的に考える力がついていく
人は自他共に、問われることによって、考えるようになります。
- 雲が動くのってなんでだと思う?
- なんで、人って泣いたら涙が出るのかな?
- あれだけ練習をがんばれたのってなんで?
このようにして、理由を聞くくせをつけていきましょう。
②どう思う?
「どう思う?」と聞いてみましょう。
このように問われると、何かしら答える必要が出てきますよね。
これが大切なのです。
こうすることで、「自己表現力」が高まっていきます。

「質問はありますか?」と言っていませんか〜!
「質問はありませんか?」という、この質問はしてはいけません。
ありません!と子どもたちは答えて終わってしまうからです。
- 友達からこんな風に言われたらどう思う?
- このお話を読んでみてどう思った?
- たくさんの友達から褒められたらどう思う?
「どう思う?」と聞いて、言葉で表現する力を高めていきましょう。
③どうしたらいい?
「どうしたらいい?」は解決策を問う聞き方です。
このように問いかけることで、子どもたちは前向きな思考に変わっていきます。
前向きな思考がない人というのは「困った=悩む」という人でネガティブな考え方をします。
ですが、前向きな思考ができる人は「困った=考える」ことができる人でポジティブな生き方ができます。
この「どうしたらいい?」と問うことは、子どもを心理的にも前向きに変えていける言葉であるわけです。
- 宿題もゲームもやるためには、どうしたらいい?
- 明日、忘れ物をしないようするためには、どうしたらいいかな?
- 自分の気持ちを伝えるためには、どうしたらいいと思う?
このように声をかけて、前向きな思考、前向きな子どもを育てましょう。

まとめさせる声かけ
「賢い子」というのは国語や算数など、様々な問題を解いていても「ざっくり言うと、こんな感じね」と大まかなポイントをつかむことできる子です。
一つ上の視点から見下すことで、ポイントを見つけることができます。
つまり、抽象的に考えることができるわけです。
「抽象的に考えられる子」は一段下がったものの見方ができる子、つまり「具体的にも考えられる子」です。
このように賢い子は「抽象」と「具体」を行ったり来たりすることができます。
では、具体的に「抽象」「具体」で考えられる子を育てるための言葉かけを紹介します。
④要するにどういうこと?
子どもに「要するにどういうこと?」と問うてみましょう。
「要するに」という言葉が難しい場合には、「同じところは?」「共通点は?」などと聞いても良いでしょう。
「要するに」と問われると、余分な枝葉をそぎ落とし、根幹となる部分だけを見つめ、考える力が高まります。
「チワワとポメラニアン、ミニチュアダックスフンドがいるねぇ。同じところはどこかな?」
「そうだねぇ、全部犬だよね〜!」
このような会話から「まとめる=抽象度を上げる」トレーニングをしていきましょう。
子どもたちの「考え、まとめる力」が高まります。
- ゴールするにはいろんなコースがあることが分かったけど、つまりどういうこと?
- 鍋って色々な種類のものを入れていくんだけど、つまり鍋ってどんな料理?
- みんな帰ったらいろんなカセットで楽しんでるけど、みんなの共通点は何?
⑤例えばどういうこと?
「例えばどういうこと?」という言葉は、「4 要するにどういうこと?」の真逆を問う聞き方です。
「具体例」を問うことで、抽象から具体を引き出すことになります。
「野菜を買うっていうけど、例えば野菜って何があるかな?」
「キャベツもニンジンも白菜も全部野菜だねぇ!」
このように具体例をどんどん引き出せる力がある子は、どんどん新しいアイデアを思いつける子です。
- 三角形の公式を習ったけど、たとえばどんな問題ができそう?
- 書くものを持っていくんだけど、書くものって例えば何がある?
- 動物が好きって言ってるけど、例えば何が好き?
「4 要するにどういうこと?」「5 例えばどういうこと?」をセットとして、「抽象⇄具体」を行き来できる言葉かけを意識していきましょう。

【まとめ】言葉かけをかえて子どもの「考える力」を高めよう!
子どもたちを賢く育てるには「考える力」を高める必要があります。
それは、授業中や宿題をやっている最中だけでなく、起きている時間全てを「考えている時間」にシフトチェンジしていくということです。
そのためには、「考える力」を高める必要があり、そのための言葉かけ5選を紹介してきました。
- なぜだろう?
- どう思う?
- どうしたらいい?
- 要するにどういうこと?
- 例えばどういうこと?
このような言葉かけを意識していくことで、子どもたちは「気づく楽しさ」「知る楽しさ」「考える楽しさ」を学んでいきます。
本書では、「さらに考える力を高める言葉」として5つ紹介されています。
- 楽しむには?
- なんのため?
- そもそも、どういうこと?
- もし〜どうする?
- 本当だろうか?
気になられた方はぜひ、実際に本書を手に取ってみてください!
きっと新しい学びがあるはずです。
ちなみに、Kindleアプリならなんと0円で読書ができちゃいます!
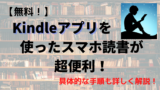
こんなチャンスはなかなかないので、この機会にぜひゲットしておくことをおオススメします!
それではまたっ!!
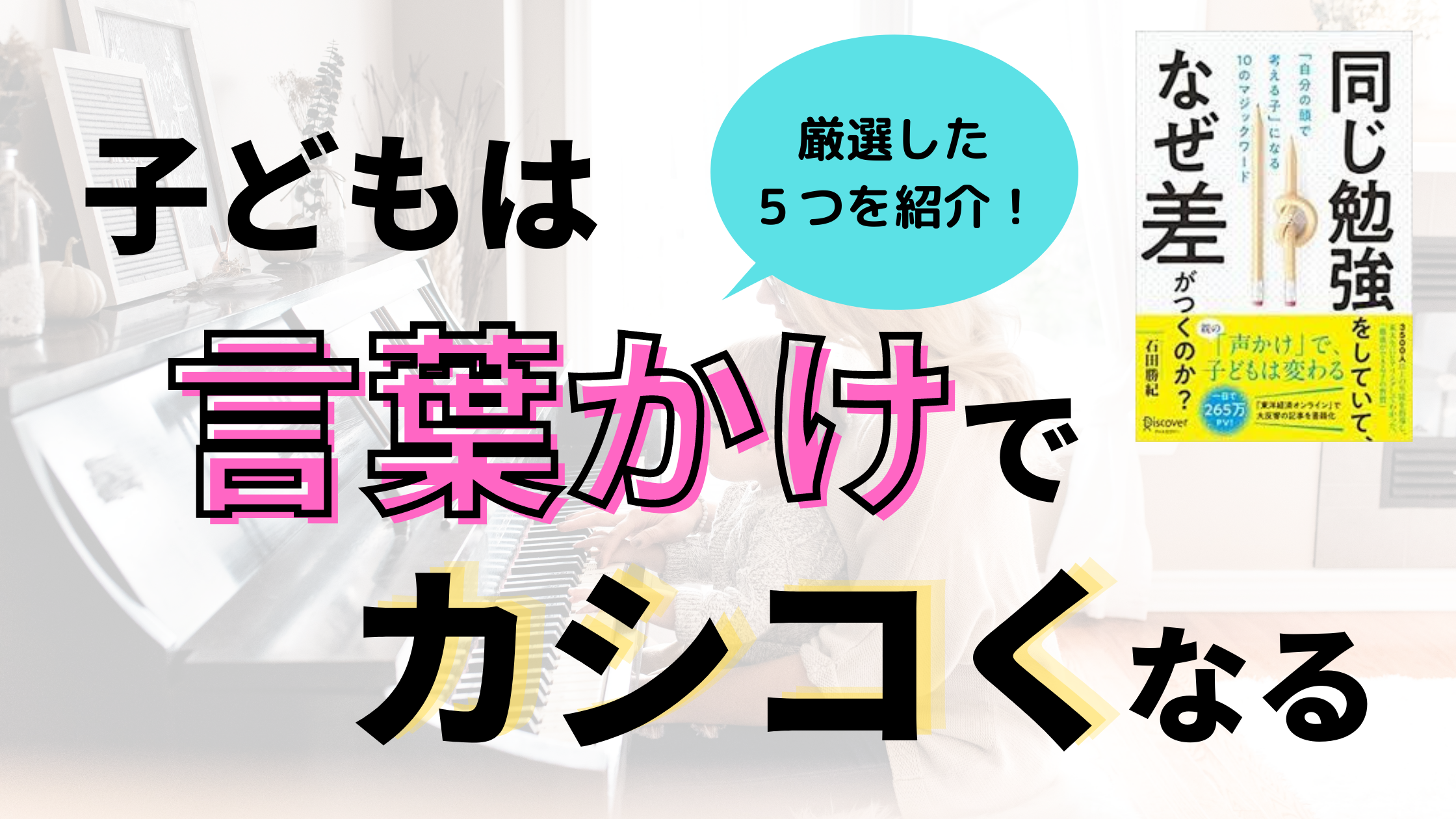
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f18f2e.813fb7a4.19f18f2f.628ecff6/?me_id=1213310&item_id=19924512&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5896%2F9784799325896.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


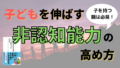
コメント