
春から先生か…どんな同僚に出会うのか不安だなぁ…
春から学校現場で働き始める大学生のみなさん!
そして、まだ「若手」と言われている先生方!
まだまだ未来ある若い先生たちが学校現場で絶対に関わってはいけない同僚、教師TOP3をお伝えします。
ボクは大学を卒業して小学校で勤務し、現在10年目を迎えたランチョーです。
そして、その10年間はしんどい思いばかりをしてきました。
今、改めて振り返ってみると「一緒に働いている先生との関係」でしんどくなってしまっていることがとっても多いことに気づきます。
ボクは何も知らずに関わっていたばかりに、自分がしんどくなってしまいましたが、みなさんには同じような思いはさせません!
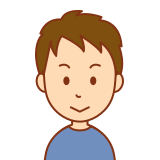
こんな先生には気をつけないと!!
と、心得て現場に出ることは、自分を守るためにとっても大切なことです。
ぜひ、しっかりと予習して現場に出られるようにしてください!

絶対に関わってはいけないのは「グチを言う教師」
学校現場に出た若い先生が絶対に関わってはいけない教師。
学校現場において「グチ」は百害あって一利なしです。
たまには、不満や不安を口に出して相談することは誰でもあります。
でも、「グチ」を言うことでストレスの発散をしたり、自分自身が気持ちよくなったりしてしまうのは、全く別の話です。
そして、そんなイタい教師が学校現場にはかなりの数存在していることは知っておく必要があるでしょう。

でも、グチって誰に対してのグチなの?
それでは、具体的に誰のグチを口に出してしまうのがいけないかを解説していきましょう!

【第3位】管理職のグチを言う教師
管理職とは、校長や教頭、副校長などの役職についている教師のことを指します。
そんな、管理職のグチを日常的に言っている教師がいます。
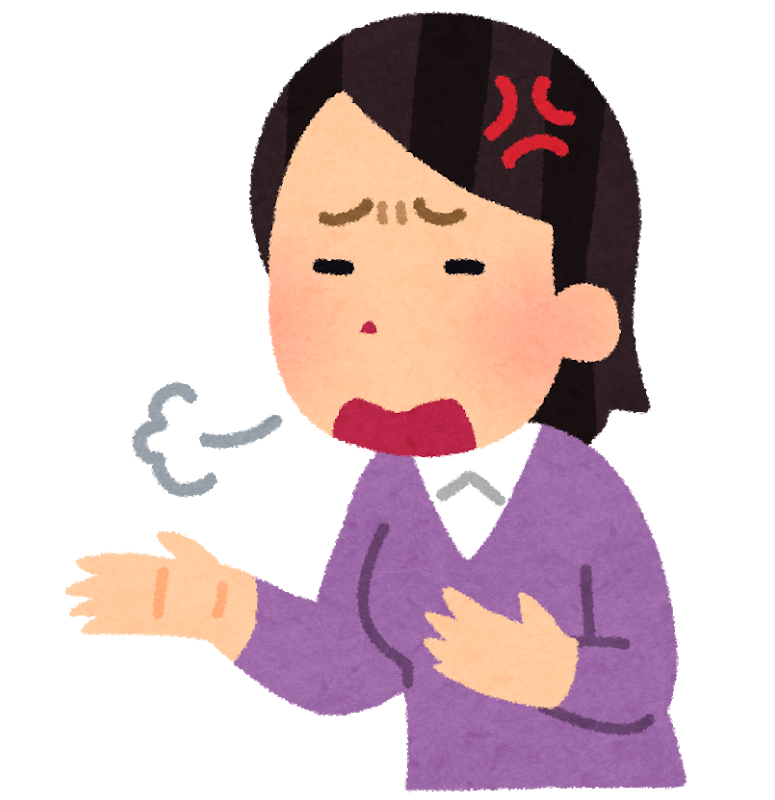
なんなのあの校長!ありえないわ!
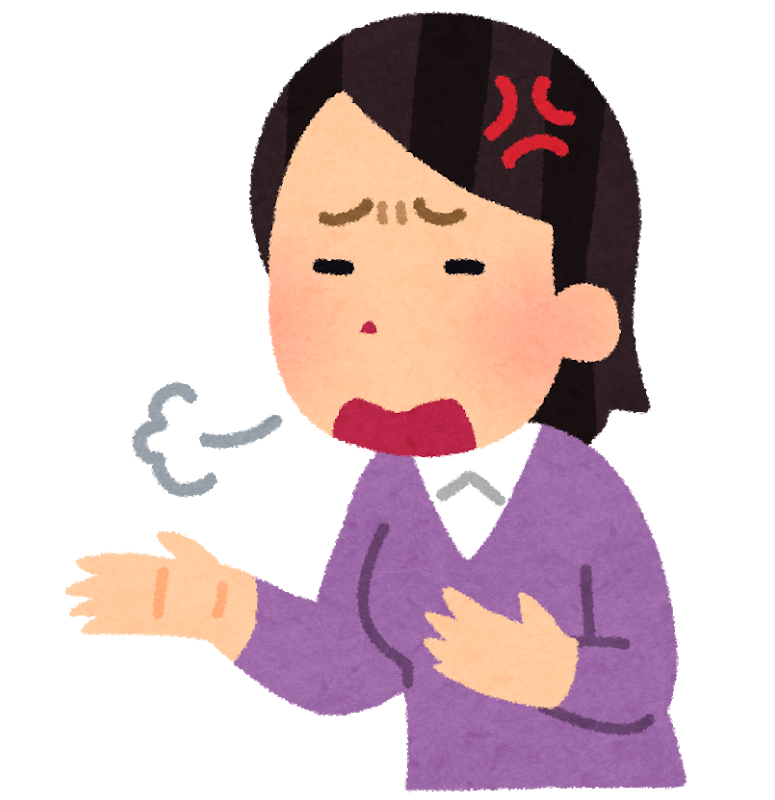
うちの教頭、全然ダメだよね〜
確かに管理職は人間性や責任感、リーダーシップを問われる役職です。
そういうものを兼ね備えた管理職が学校を引っ張ってくれることが理想であることは間違い無いでしょう。
しかし、もともと教師だった人が管理職になっているわけですから、そこまでパーフェクトな人材を求めるのは現実的に厳しいこともご理解いただけるはずです。
自分も一教師であることを考えると、そんなパーフェクトであるはずがないですよね?
そういう管理職に対して「管理職なんだから!」とグチを言うのはナンセンスです。
また、そういう管理職に対してグチを言う人は自分の力の無さを管理職のせいにしている人です。
遠回しに「自分は力がありません」と言いふらしてしまうほど格好悪いことはありません。
自分の仕事の質は、管理職ではなく自分の力で高めていくものです。
決して、自分自身が管理職のグチを言うことなく、さらに管理職のグチばかりを言う人からは離れるべきです。
自分の力は自分で高めていきましょう!

【第2位】同僚のグチを言う教師
中には同僚のグチを平気で言っている教師も学校現場にはたくさん存在します。
そういうボクも前任校で同じ学年を組んでいた教師からグチを言われ、ずいぶん苦労したことがあります。
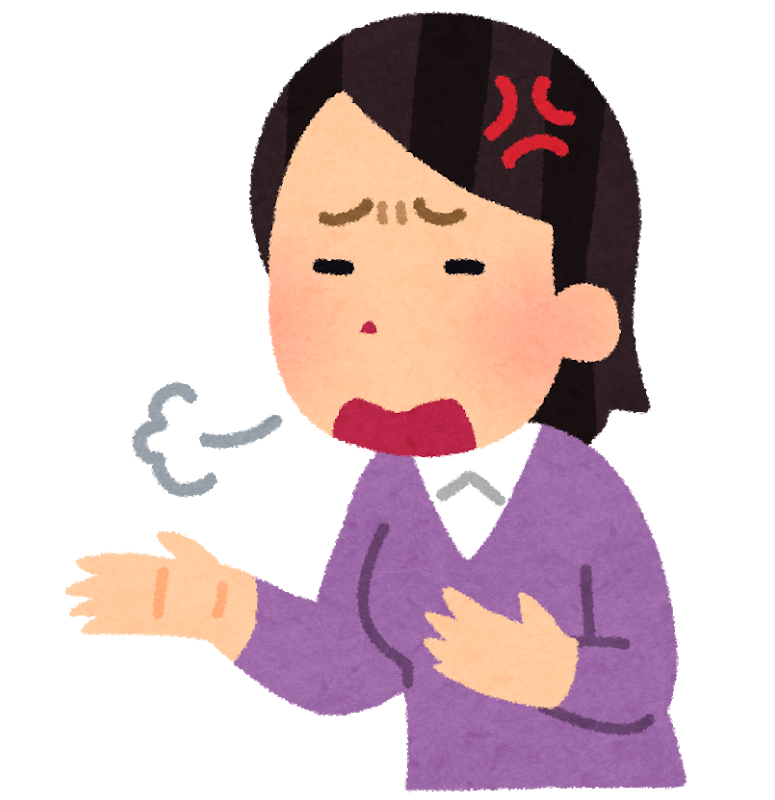
◯◯先生、あんなこと言ってるけどありえないよね〜
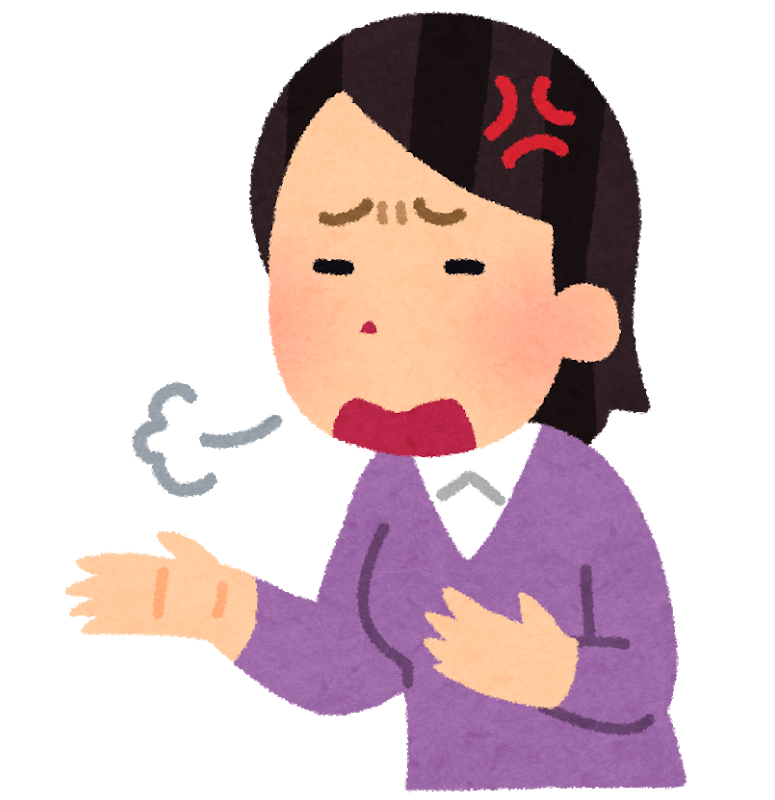
一緒に働いていくのとか無理!
教師という職業は、毎年毎年だれと同じ学校で働き、だれと協力していかなければならないか分からないちょっと変わった職場で働きます。
中には、合わない教師や好きになれない教師がいるということも事実です。
そんな教師と一緒に働いていかなければならない苦しい現状があることも事実です。
でも、だからと言って同僚の悪さを見て、同僚のグチを言うことは全てにおいてマイナスになることを理解しなければならないはずです。
同僚のグチを言う教師がいる職場の生産性の低さはあまりにも大きすぎます。
・他の同僚の士気が下がる
・管理職の悩みが増える
・自分の生産性も落ちる
・職場全ての生産性が落ちる
そんな諸悪の根源となる教師がいるのは不幸としか言えませんが、自分にできることはその教師と同調するのを絶対に避けることです。
間違ってもあなた自身が同僚のグチを言う一人にならないようにしましょう。

【第1位】子どものグチを言う教師
絶対に関わってはいけない教師のキングオブキングは「子どものグチを言う教師」です。
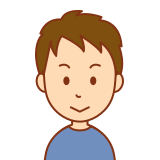
先生なのに子どものグチを言う人がいるの?
そう驚く人がいるかもしれません。
でも、10年以上ボクが働いてきて今、断言できることがあります。

子どものグチってかなり飛び交っているのが現実だよ…
・子どもの不真面目さ
・子どもの問題行動
・指示に従わない子ども
・言ったことができていない
教師として「うまくいっていないこと」を子どものせいにしてグチを言う教師。
その数はかなり多いということが現実です。
いざ、現場に入ったら確かに子どもの行動と自分の思いのあまりの大きなギャップに戸惑うこともあります。
でも、それを「子どものせい」にするのは、教師としての仕事を放棄していることに他ならないと心得るべきでしょう。
「うまくできない子ども」「未熟な行動をとる子ども」をより正しい道へと教え導くことこそ教育であるはずですよね。
または一方で、「うまく行動できない子ども」が目の前にいるということは、「うまく行動させられていない教師である自分自身の力不足」であるとも言えるわけです。
その本来の教育から目をそらし、子どもへのグチという行動をチョイスしてしまう教師は愚の骨頂です。
職場にそういう教師がいるのなら、いち早く距離を取るべきです。

年間5000人が病休をとる理由
今、学校現場は毎年5000人の病気休暇を生んでいます。
その原因は様々です。
・保護者とのトラブル
・子どもとの関係
また、それらの原因が重なって体調不良となっていることもあります。
しかし、それらに匹敵する心身の不調の原因となる一つに「一緒に働く教師との関係」があります。
学校現場は特殊です。
・毎年、同僚がコロコロ変わる
・同僚になった教師とは数年間の密接な関わりが課せられる
気の合う教師もそうでない教師も、毎日同じ職員室で、同じ目標に向かって、力を合わせて働かなければならなりません。
自分にとって心許せる教師ばかりが職員室にいればかなり幸せな教師生活が1年間だけは保障されます。
しかし、良い関係を築ける教師ばかりがいる学校など皆無です。
話しにくい、気が合わない教師が一定数います。
そういった教師と数年間は同じ学校で働くことが避けられない仕事現場が「学校」という場所です。
病気休暇をとらなければならなくなった多くの先生たちの中には、関わりたくない教師と毎日関わらなければならないストレスに耐えられなくなった先生たちも多いはずです。
どうか、「関わってはいけない教師」を自分の中にしっかり持ち、心の距離をしっかりとりながら教師として働くことで自らの心身を元気に保って欲しいと切に願います。

【まとめ】特殊な学校現場では関わってはいけない教師が多数いる!
以上、学校現場が関わってはいけない教師と必然的に関わらなければならない環境になっていること、そして具体的な関わってはいけない教師はどんな教師であるのかをお伝えしてきました。
・管理職のグチを言う教師
・同僚のグチを言う教師
・子どものグチを言う教師
以上、学校現場が関わってはいけない教師と必然的に関わらなければならない環境になっていること、そして具体的な関わってはいけない教師はどんな教師であるのかをお伝えしてきました。
これらの教師から意識的に距離をとり、あなた本来の仕事が行えるようにあなた自身で環境整備を行っていってください!
子どもの成長に関わる先生自身が、まずは笑顔と元気でいられますように!
それではまた!
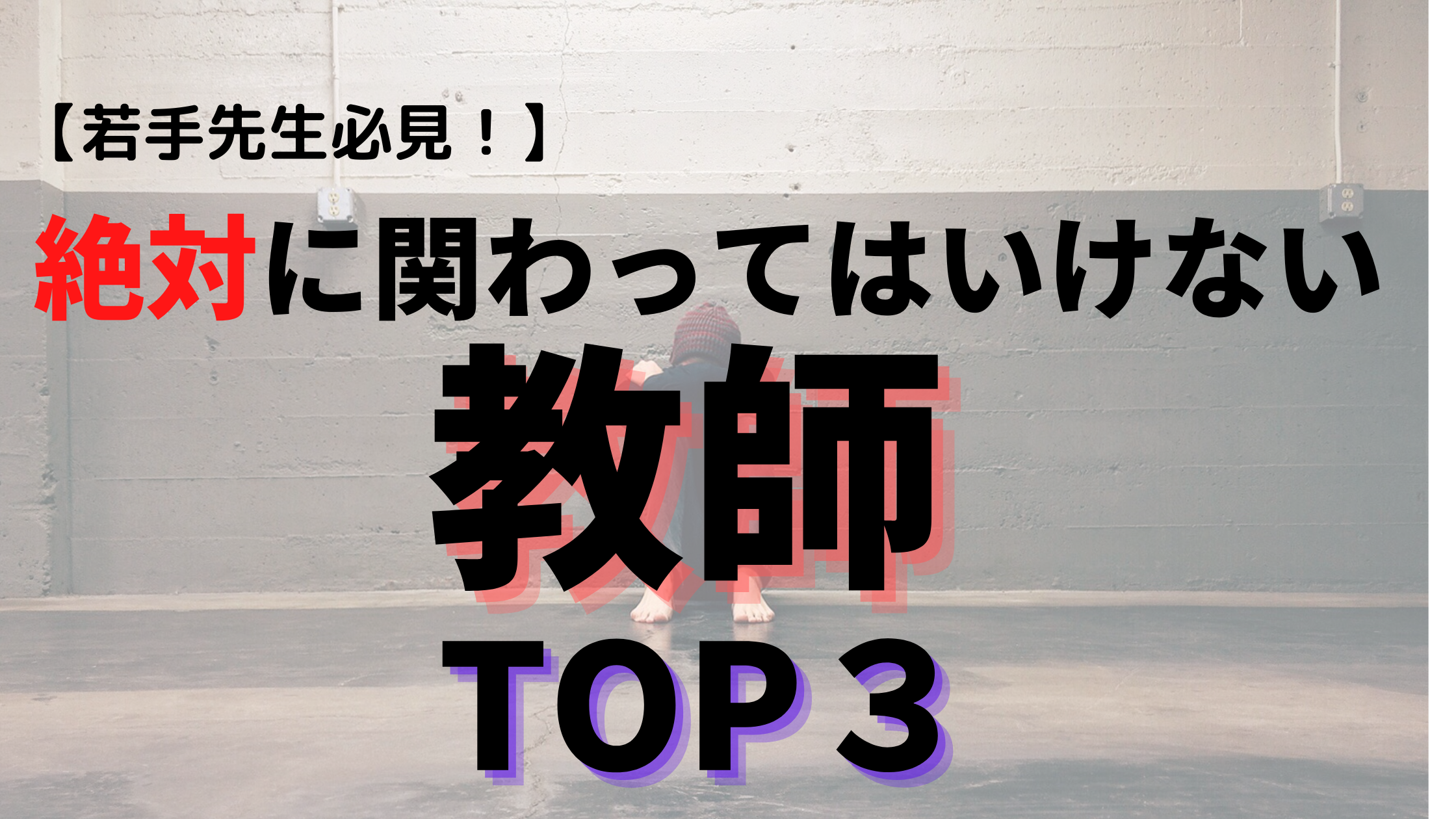

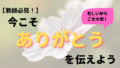
コメント