夏休み、「授業」や「学級経営」についての書籍を読んで、力を高めようと思っておられる先生方も多いのではないでしょうか。
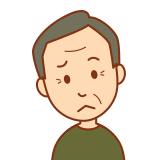
でも、指導に役立つ本って何がいいか分からなくて…
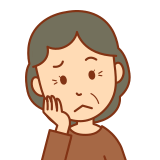
本屋に行ってもたくさん本がありすぎて選べないわ…
そんな先生も多いはずです。
書店に行けば山のように本が並んでおり、気になるテーマがいくつも見つかり、結局選べなかった…ということもよくありますよね。
今回は、数ある教育書の中でも「とりあえず読んでおけば間違いない」という1冊を紹介します。

とっておきの1冊は向山洋一氏の『授業の腕を上げる法則』だよ!
騙されたと思って一度、手に取ってみてください。
1学期の自分の指導を見直すきっかけ、2学期からの自らの指導をレベルアップさせられる機会になるでしょう。
この記事では、『授業の腕を上げる法則』の第1章にある「授業の原則」を10個紹介します。
この「10の原則」は授業だけではなく、学級経営を進めていく上でも、教師にとって必要な技術が分かりやすく具体的に書かれているので、とっても参考になります。
【授業の10の原則とは】
趣意説明の原則
趣意説明の原則とは「指示の意味を説明すること」です。
子どもたちは「自分の行為の意味を理解してこそ、考えも精神も安定」します。
本書には「知性的な集団はのびやかな自由さがあり,自分のやっていることを自分で納得している集団である」と書いてあります。
子どもたち自身の行動が「先生に言われたからやる」のではなく、「意味があってやっている」というように納得感があることが大切です。
・ごみを拾いなさい→アマチュア教師の指示
・教室をきれいにします。ごみを拾いなさい。→黒帯教師の指示
・教室をきれいにしよう。自分でやりたいことをやってごらん。→プロ教師の指示
「意味を理解しつつ、自分の行動を選択させる」というプロ教師の指示ができることを目指しましょう。
一時一事の原則
一時一事の原則とは「同じときに二つも三つも指示を与えず、一つの指示だけに集中させる」ことです。
この指示では、動けない子が必ず出てきてしまいます。
⭕️ ・鉛筆を置きなさい。 →全員置くのを待つ
・算数の教科書、34ページを開きます。 →全員開くのを待つ
・問題1番を読みましょう。 さんはい! →全員で読ませる
このように一つの指示に集中させることで、子どもはしっかり動くことができます。
本書には「一時に一事の指示をするという原則は力を分散させず、一点に集中することで事を成し遂げるという闘いの原則にも共通する」と書かれています。
ボクの実感では「子どもを動かせるかどうか」を日常的に問われている学校現場はもはや「闘い」です。
一時一事の原則を意識して、日々の闘いを制しましょう。
簡明の原則
簡明の原則は「指示・発問は短く限定して述べよ」というものです。
前に述べた「一時一事の原則」とも通じる原則です。
「指示は短く」といっても、その内容にこだわることが大切です。
このような指示は「短いがダメ」です。
⭕️ 1人が三回跳んだら先生のところに集まります。
⭕️ 両足で踏み切ることだけ集中しましょう。
このように、指示や発問は限定して、簡潔に行いましょう。
全員の原則
全員の原則とは「指示は全員にせよ」というものです。
・物を一度置かせてから指示を聞かせる
・体を前に向けさせてから指示をする
など、全員が指示を理解することを徹底しましょう。
一見面倒なようでも,指示は必ず全員に伝えなければなりません。
「全員に伝えたつもり」「私としてはみんなに言った」ではだめです。
そして、指示をする上で大切なことがもう1つあります。
それは「最後の行動まで示してから動かせ」ということです。
指示したことが終わった後、「子どもたちが何をしていいか分からず、騒ぎ出す」という光景もよく見られるものです。
「終わった後どうするか」というところまで示して、指示は完結します。
所・時・物の原則
所・時・物の原則とは「子どもを活動させるためには、場所と時間と物を与えよ」という原則です。
所の原則では
本書では、「机の配置がいつも同じなのもダメ。作業させるなら場を与える。机を4つ並べる、教室の後ろにすべてもっていく、端に寄せるなど、バリエーションを持て」とあります。
時の原則では
物の原則では
つまり、「子どもたちに相談する時間,作業する場所,必要な道具をしっかり確保すべきで、それをしないで自分たちで工夫しなさいは「指導の放棄」である」という原則です。
空白禁止の原則
空白禁止の原則とは「たとえ一人の子どもでも空白の時間を作るな」というものです。
本書では「1分間でも何をやっていいかわからないという状態を作ってはいけない」とあります。
前に挙げた「全員の原則」とも通じる原則です。
手持ち無沙汰の子どもがフラフラし始めるということはよくあること。
「先のことまで考えて手を打つべき」とあるように、「空白時間を作らない」ことを頭に置いて指示をするようにしましょう。
指示の原則
指示の原則とは「まず全体に大きな課題を与えよ。然る後に個別に指導せよ。」というもの。
・指示の途中で子どもが質問し、それに答える
・個別の質問がたくさん出て、それから全員に改めて指示し直す
このような光景はよく見られます。
現場では、「個別の支援」「個への声かけ」が重要視されています。
でも、それは「全体への指導がある」ということが前提での「個別の支援」であるはずです。
「全体→個別」という形はブラさずに指導をすることが大切です。
確認の原則
確認の原則とは「指導の途中で何度か達成率を確認せよ」というものです。
教師としては「全体に指導したからみんなわかっている」と思い込んでしまうことがあります。
しかし、途中で子どもたちの理解、達成率を確認しながら指導を進める必要があります。
その達成率を確認する際にも注意があります。
子どもにこのように問うてはいけません。
みんな「分かりましたね?」と言われると「ハイ!」と答えてしまうからです。
と聞き、子どもに発言する余白を持たせましょう。
また、本書では「達成率を確認する方法をいくつももっておく」ことが大切だと指摘されています。
・できたら手をあげなさい
・指をさしなさい
・隣と確認しなさい
・終わった人から座りなさい
このように、子どもの理解度・達成度を知るための方法を多く持っておきましょう。
このように確認することで、指導にメリハリをつけることもできます。
個別評定の原則
個別評定の原則とは「誰がよくて誰が悪いのかを評定せよ」というものです。
指導と評価は両輪です。
指導だけで評価しないのはいけません。
本書では「卒業式の呼びかけ」を例にとって説明がされています。
○番、○番、○番 立ちなさい。声が聞こえない。分かったら座りなさい。
○番、○番、○番 出だしが早すぎる。
○番、○番、○番 切れ目がない。○番言ってみなさい。はい合格。
○番、○番、○番 (数秒おいて)君たちは合格だ!
このように具体的に指摘することで、子どもたちは動きの質を高めていけます。
激励の法則
激励の法則とは「常に励まし続けよ」という法則です。
・人間が動く方法はやる気にさせること
・やる気にさせるためには励まし続けること
これが最後の法則です。
子どもが持っている欠点を克服するように絶えず励まし続けましょう。
「大丈夫だよ、がんばってみよう」「この前よりもよくなったよ」と言い続けましょう。
子どもたちは励まされることで前に進むエネルギーをためていけます。
【「10の原則」を意識して、指導を1段階レベルアップさせよう!】
TOSSで有名な向山洋一氏の著書『授業の腕を上げる法則』に示されていた「10の原則」をまとめてきました。
・趣意説明の原則
・一時一事の原則
・簡明の原則
・全員の原則
・所・時・物の原則
・空白禁止の原則
・指示の原則
・確認の原則
・個別評定の原則
・激励の法則
これらの全てを意識しようなどと思うと大変ですし、気が遠くなりそうです。

「これはできそう!」と思えるものから実践してみよう!
自分ができそうと思えるもの、具体的にできそうなイメージができそうなものからやってみましょう!
そしてぜひ、本書を手に取り、別の実践や指導論についても学んで欲しいと思います。
教師が新しい指導にチャレンジし、指導の腕を磨くことは子どもたちの幸せにつながります。
そして何より、これを読んでくださった意識の高い先生の幸せにつながると確信しています。
共に学び、共に実践を続けていきましょう!
それではまたっ!
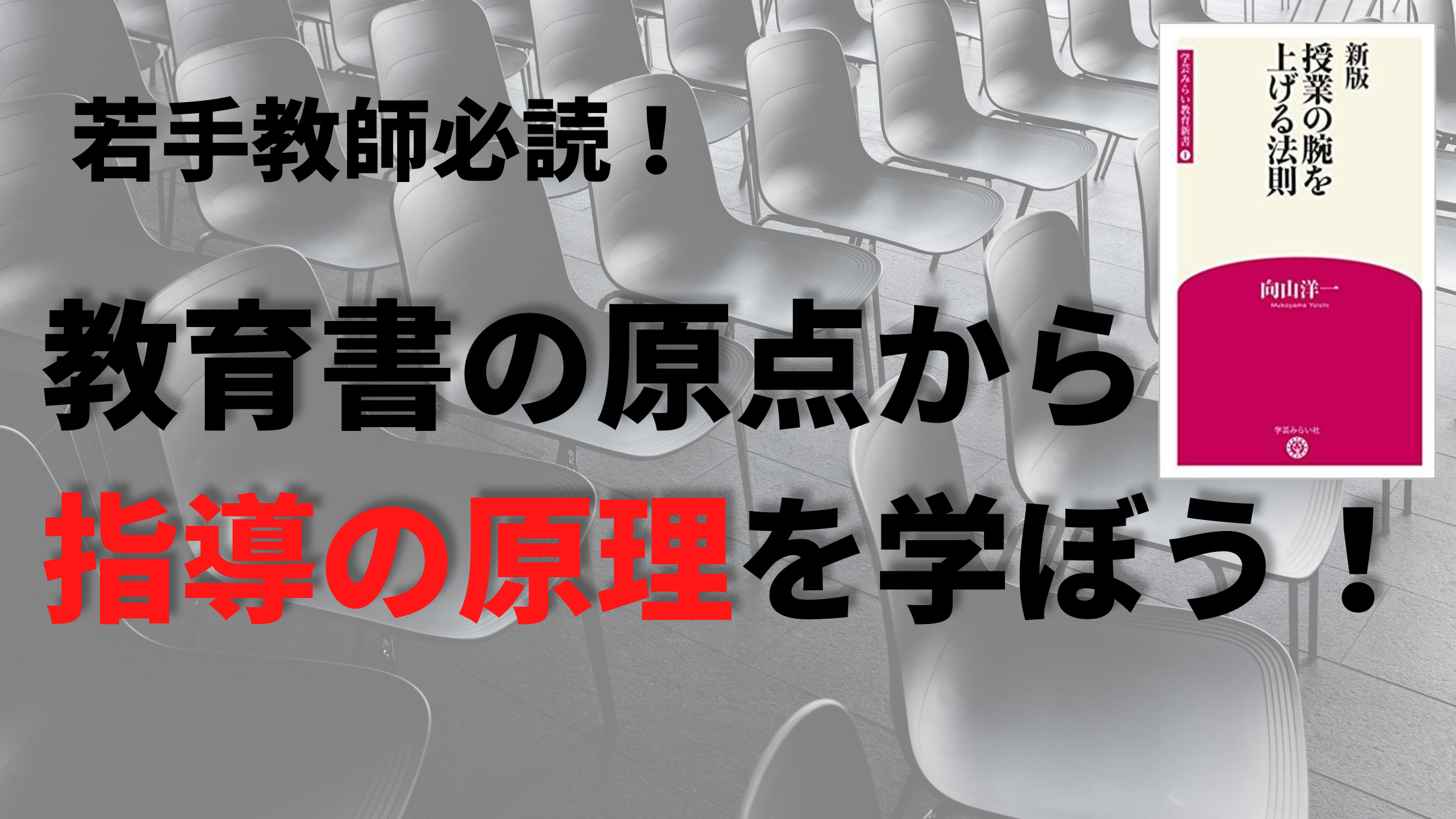
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f18f2e.813fb7a4.19f18f2f.628ecff6/?me_id=1213310&item_id=17556528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4756%2F9784905374756.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

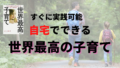
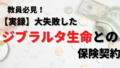
コメント