
先生〜!◯◯君にいじわるされました〜!

◯◯君が「死ね!」って言ってきた〜!
学校ではこんな風にトラブル対応に追われることもしばしば。
小学校低学年ならそんなトラブルは日常的にありますし、高学年や中学校になるとまた様子は変わってきます。
男女でも違うでしょうし、子どもによっても様々なトラブルがあります。
しかし、今回紹介する「トラブルがあった時の児童への対応」は、どんな児童や年齢にも通じます。
もちろん、これだけで全てのトラブルが解決するとは言い切ることはできませんが、全てに通じる「基本」であると思っています。
日々、トラブル対応に頭を悩ませる先生方の指導が少ししやすくなるきっかけになれば嬉しいです!
では、早速紹介していきます!

【加害児童への対応の鉄則・手順】
①いじわるした子の言い分をしっかり聞く
まずはここが第1ポイントです。
という風に、「教師の言い分」を言うための「指導」をしようと思って聞くといけません。
まずは、いじわるした子が「なんでそんな行為におよんだのか」という「言い分」をしっかり聞いてあげましょう。
その子なりの「言い分」が必ずあるはずです。
子どもに「言い訳」させることにはならないか?と心配する人がいるかもしれませんね。
でも、大丈夫です。
「なんでそんなことしたの?何か理由があったんじゃない?」と心の内を聞いてあげましょう。
この時点で、ずいぶん落ち着いて自分のしたことを反省する子も現れます。
②その子が「決して悪い心でやっていたわけでない」ことを認める
この②が最重要ポイントです。
「動機はどうであれ、悪いことは悪いんだ」と決めつけて責め立ててしまうのは1番よくありません。
①はできていても、「あなたにそんな理由があったかもしれないけど、そんなことしていいと思ってるの!?」などと言ってしまうことがあるわけです。
そうなると、子どもはふて腐れて反省することにならないからです。
最悪、もっとひどいことをするということもあります。
①で「言い分」をしっかり聞いた後、その気持ちによりそってあげることが大事です。
その子なりの「まっとうな理由」があったことを認めるわけです。
こうして「自分の気持ち」を認めてもらった子というのは、程度の差はあれどもグッと心を開いてくれるでしょう。
③相手の子はどう受け止めたかを考えてもらう
しかし、①と②だけではいけません。
①と②では、加害児童のいじわるやいじめ、そのものを認めているかのような印象を与えてしまうからです。
そうなると、教師がいじわる・いじめに加担したことにもなります。
ですので、③では「まっとうな理由があったこと」と「行為が正しかったかどうか」を別だととらえさせる必要があります。
そこで、「相手の身になって考える」という③があるわけです。
たいがいの子は「いじわるされたA君は嫌だったと思う」とか「嫌なこと言われたら傷つく」などと、相手の身になって考えてくれます。
ここまで来れば「加害児童への指導」はほぼ終わりです。
というような話ができ、
と聞くと、「A君に謝る」と言ってくれる子も多くなってくるでしょう。
この③が素直に認められない子に対しては特別に④が登場します。
(オマケ)④その時の様子をリアルに再現してもらう
自分の気持ちを言ったものの、自分がやったことは認められない。
そんな子どももいるかもしれません。
そんなときは、自分がやってしまった時のことを「もう一度、その場で再現させる」という方法をとります。
改めて冷静になってから「その行為」をするというのは、本人も客観的に自分がやったことを捉え、以外に反省してくれるケースもあります。

【加害児童への対応の基本まとめ】
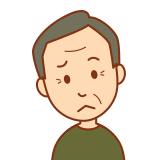
そんな風にうまく指導が進められるかな?
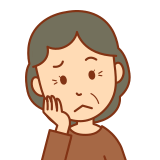
うちのクラスの子どもでは無理だよ!
そんな風に思われる方もおられるかもしれません。
もちろん、そうですよね。
私自身が担任している子どもだって、一筋縄ではいきません。
しかし、今回まとめた①〜④を基本にすれば、かなり幅広い範囲の指導に応用できると思っています。
という手順さえ間違わなければ、たいていのトラブルへの対応はできると思うのですが、どうでしょうか。
もし、それでも困ったケースや疑問などがあれば、ぜひ教えてください!
一緒に考えさせてください!!
それではまた!

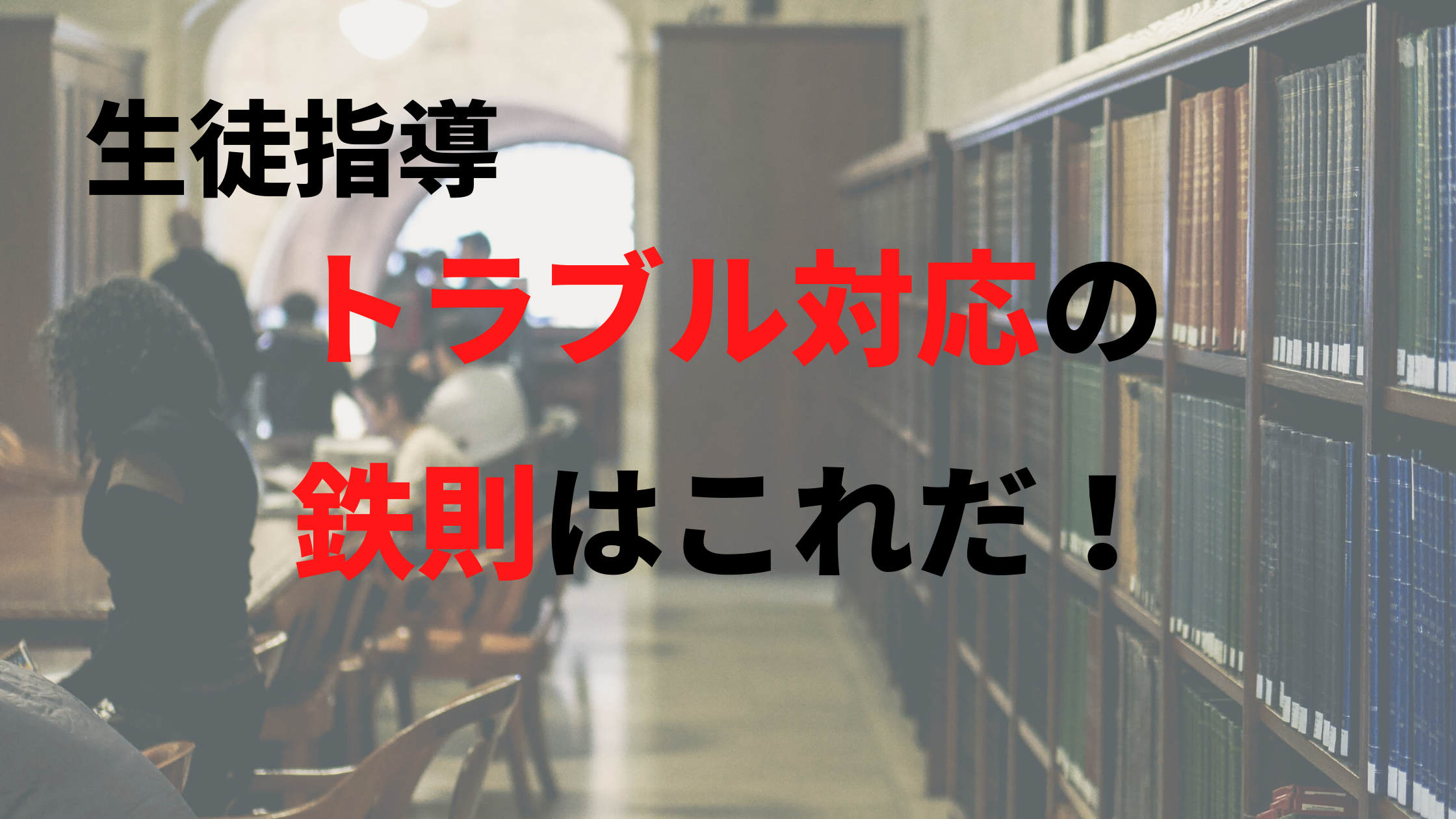
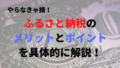
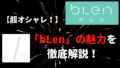
コメント