子どもを叱る時ってどうすればいいか迷ってしまいませんか?
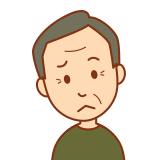
子どもを叱る時、つい感情的に言ってしまうことが多くて…
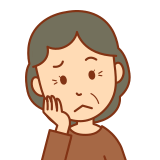
叱っていたら何だかカッとして何を言っているのか分からなくなる時があるわ…
何年も学校現場で働いてきた先生たちも、子どもたちへの「言葉かけ」には常に悩みをもっているものです。
その悩みの多くは普段子どもと接する中で頻繁に起こる「叱る場面」にあります。
「怒ってはいけない、叱るのだ」などと先輩教師や書籍に学び、「分かりました!」と思いながら、結局どうしていいか分からない。
特に、経験の浅い先生や学生さんはなおさら、子どもの「叱り方」ってどうしていいのか分かりませんよね。
ボク自身も10年教師をしてきて
- 時には叱らないといけないと分かっているけど
- 感情的にならず、でもきちんと叱る方法は分かっていない
これが正直な気持ちです。
常に、日々迷いながら子どもと接しているのが現実です。

この記事では「叱り方」のポイントと具体例を書籍をもとに分かりやすく紹介するよ!
今回、参考にした書籍は三好真司氏の著書『教師の言葉かけ大全』です。
この書籍には具体的なほめ方やしかり方など、子どもとの接し方の具体的な例がたくさん挙げられています。
毎日子どもと接している先生なら若手からベテランまで、さらに子育てをしているパパ・ママにも参考になる部分が大いにある1冊でした。
ちなみに、「ほめ方」についてまとめた記事もありますので、ぜひ合わせてご覧ください!
それでは、早速「子どもの叱り方」について学んでいきましょう!

【はじめに】叱るのはほめるのと同じくらい大切
- ほめるのは子どもが喜んで嬉しそうだからどんどんできる
- でも、叱るのは子どもの悲しい顔を見ることになるから億劫になってしまう
そんな風に感じてしまう人はいませんか?
ボク自身、我が子と接している時も、勤務校で子どもと接している時も「叱ることに躊躇してしまう」瞬間が何度もあります。
しかし、本書では「叱るのはほめるのと同じくらい大切なことだ」ときっぱり書かれています。
分りやすく車に例えた説明もなされています。
- ほめ言葉はアクセル
- 叱り言葉はブレーキ
つまり、
- やっていることは正しいよと進むように仕掛けるのが「ほめ言葉」であり、
- やっていることは不適切だから進んではいけないよと伝えるのが「叱り言葉」である
車がアクセルだけだと事故を起こしてしまい、ブレーキだけだと全く進まないように、子育てや教育にとって「ほめ言葉」と「叱り言葉」はどちらも必須であるということです。
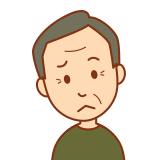
叱り言葉が大切なのはよく分かったけど、叱り方で注意するべきことってあるの?

コラー!って大きな声で叱ってるだけでは意味がないもんね!
いくら叱るのが大事だとはいえ、子どもを叱る際に大人が肝に命じておくべきことあります。
これは「ほめ言葉」にはなかったとても大切な点だといえます。
叱り言葉には、子どもの動きや心を抑制する働きがあります。
つまり、子どもにとってマイナスの感情がその時に沸き起こるということです。
使い方を間違えれば、信頼関係が崩れてしまったり、子どもの心を傷つけることになったりしてしまいかねないということは忘れてはいけません。
では、子どもの叱り方の具体的な方法を紹介していきましょう!

叱り方のバリエーション
無視法
「無視法」とは、子どもの望ましくない行動に対して徹底した無視をつらぬく叱り方です。
何も言わずに、目線をそらす方法もあれば、
- そうですか。
- 見たくありませんので。
- もう知りません。
- ふうん。
のように、一言伝えるだけで無視する方法もあります。
子どもの言動に対して意図的に無視することで、子どもの行動にブレーキをかけましょう。
さっぱり否定法
「さっぱり否定法」とは、子どもの言動に対して素早く否定する方法です。
理由も言わずにさっと否定するだけで指導を終えてしまいます。
- だめ、やり直し。
- できていないね。
- 甘いね。
- それで満足ですか?
軽い否定から、なぜそれがいけないのかを自分で考えさせることにつなげましょう。
取り上げ法
「取り上げ法」とは、きちんとやろうとしない活動そのものを取り上げる方法です。
活動を取り上げること自体が子どもにとって不快なので、厳しい叱責は必要ありません。
- 中止にします。
- では、終わりにします。
- やらなくていいです。
- あげません。
- また、今度にしましょう。
子どもが反省できたら、もとの活動に戻します。
しかし、注意が必要な叱り方でもあります。
取り上げられることが子どもにとって快になってしまうと元も子もありません。

やったー!やらなくていいって言われたー!!
これは最悪なので、取り上げる内容は吟味しましょう。
怒責法
「怒責法」とは、怒りを込めて厳しくしかる方法です。
自他の心身を傷つけてしまうような行為に対して、気迫を持って対峙する叱り方です。
- 自分が言われたらどう思うんだ!
- 何をしている!
- それはどういう意味だ!
- 何を考えている!
- それでいいと思っているのか!
厳しく叱る方法なので、くどくどと叱ってはいけません。
できるだけ短い言葉で伝えましょう。
理詰め法
「理詰め法」とは、叱っていることの理由を理論立てて説明する方法です。
とくに高学年以降、子どもは意味のわからない叱責に対して反感を覚えます。
- どうしてこれをやる必要があると思う?
- 先生が怒っている理由を言います。
- なぜいけないのか。理由は3つある。
このように話しながら、子どもの行動を正しい方向に導いていきましょう。
忠言法
「忠言法」とは、手を抜いているところを他の人にも知ってもらうように伝える方法です。
大人と子どもだけでなく、第三者に知ってもらうことで子どもの行動をよりよいものに導いていきます。
- 君がやらないこと、次の学年の先生にも伝えておくからね。
- お家の人に学校へきていただこう。
- 学校中に知っておいてもらおう。
- 教室全員にも伝えよう。
- 中学校の先生にも知っておいてもらおう。
本当に言わなくとも、教師のそういう姿勢を伝えるだけで効果は大きいでしょう。
本当に電話をかけたり、言いに行ったりするとより効果的です。
実際に言う場合には、大人同士で事前に打ち合わせておけるとより良いでしょう。

【まとめ】叱り方に変化を持たせて、子どもを正しく導こう!
日常的に行なっているはずの「叱る」という指導にも、実に色々なほ叱り方があることがご理解いただけたと思います。
この記事が「感情的に怒っていただけ」から「意図的でよりよい行動に導くための指導としての叱り」に変われば嬉しいです。
改めて紹介した叱り方をまとめておきましょう。
- 無視法:子どもの望ましくない行動に対して徹底した無視をつらぬく
- さっぱり否定法:子どもの言動に対して素早く否定する
- 取り上げ法:きちんとやろうとしない活動そのものを取り上げる
- 怒責法:怒りを込めて厳しくしかる
- 理詰め法:叱っていることの理由を理論立てて説明する
- 忠言法:手を抜いているところを他の人にも知ってもらうように伝える
たくさん紹介しましたが、まずは自分にできそうな方法から取り入れてみてください。
全部やろう!なんて思うと大人がしんどくなってしまいますからね。
ここまで読んでくださってありがとうございました!
紹介した『教師の言葉かけ大全』には、「ほめ方」以外にもたくさんの具体的な実践が数多く紹介されています。
気になった方はぜひ、チェックしてみてください!
それではまたっ!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f18f2e.813fb7a4.19f18f2f.628ecff6/?me_id=1213310&item_id=19915374&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0493%2F9784491040493.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

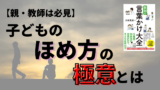
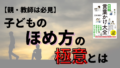
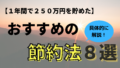
コメント