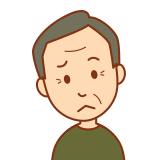
生徒指導を学級経営に生かすって何をすればいいのかな?
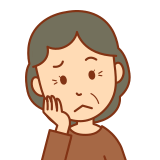
生徒指導の三機能ってよく言われるけど、なんのこと?
「生徒指導の3機能を生かした実践」とはよく言われますが、具体的にどのような実践をすることが必要なのか、いまいちイメージができないという人はいませんか?

本記事では諸富祥彦さんの著書を参考に「生徒指導の3機能」とは何なのか、そして「3つの機能を生かした具体的な実践方法」についてわかりやすく解説するよ!
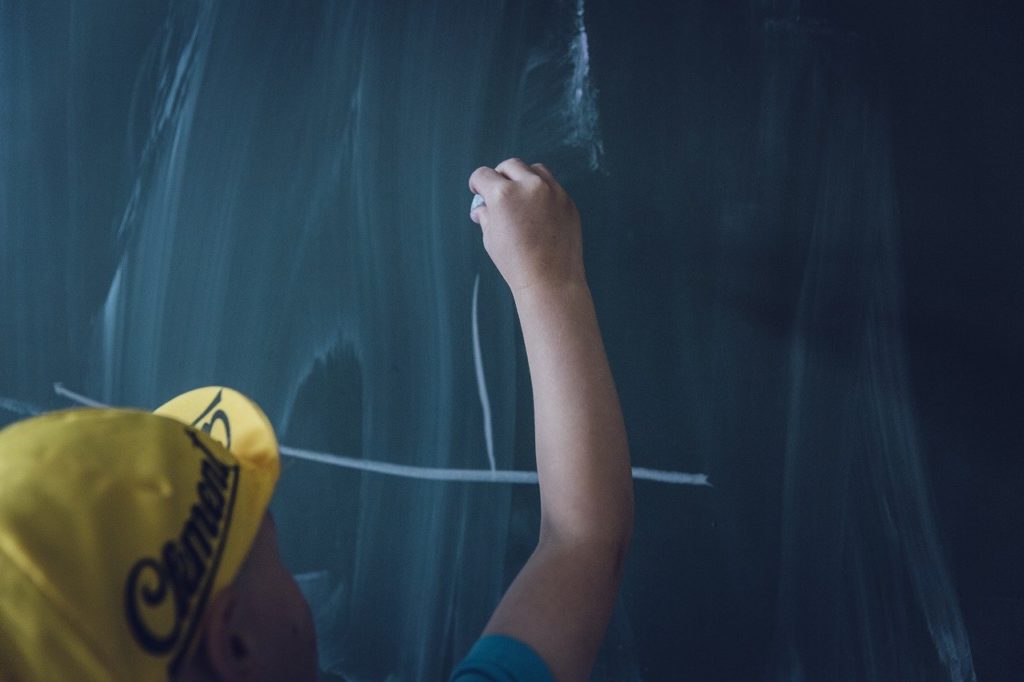
【前提】生徒指導のねらいとは
まずはじめに、学校教育の中核をしめている生徒指導の究極のねらいをおさえておきましょう。
これが生徒指導の目指す「子どもにつけさせたい力」です。
自己指導能力についてもう少しわかりやすく説明しましょう。
自己指導能力とは、「その場でどのような行動が正しいか、自分で判断して実行する力」のことです。

行動か正しいかどうかは、どうやって判断すればいいのかな…?
子どもたちが選択する行動が正しいかどうかの判断基準は「自己実現」と「他者の主体性の尊重」です。

つまり、その行動が「自分が喜び、みんなも喜ぶ」かどうかが大事なんだね!
生徒指導では、「決められた通り動ける子どもを育てることではなく、自分で考え、自分で決めて実行する力」をつけさせることを目指しましょう!
それでは、どうやったらその「自己指導能力」を身につけさせることができるのでしょうか。

自己指導能力を育てるための3つの方法(生徒指導の3機能とは)
そこで大切にされるのが「生徒指導の3つの機能」というわけです。
「生徒指導の3機能」と呼ばれているのがそうですよね。
学校現場では「生徒指導の3機能を生かした…」という言葉が先立っています。
そのため、「難しい言葉でよくわからない…」というイメージが先行しがちです。
しかし、本書によると「自己指導能力を育てるための3つの方法」として取り上げられています。
その「3つの方法」がこれです。
- 自己存在感を与える
- 共感的な人間関係を形成する
- 自己決定の場を与える
これら3つを総合して指導することで、子どもたちの「自己指導能力」を高めていこうというわけです。

3つの方法を生かすための具体的な実践
自己存在感を与える
学校現場を見ていて、「自己存在感の低い子どもが多い」と感じる場面が何度もあります。
問題行動の多い子、発達障害のある子は特に「自己存在感」が低い子どもが多いと言えるでしょう。
こういった「自己存在感が低い」子どもたちを教師は無意識に生み出しているかもしれません。
例えば、このような場合です。
ネームプレートを活用しよう
教師のこういった何気ない進め方一つをとっても、A君にとっての「自己存在感を失わせる指導」となってしまうことがあります。
教師は常に「A君の意見はB君の考えと似ているということだね!じゃあA君の名前をB君の考えの横に貼っておこう」と言って、A君の意見を大事にしているというレスポンスを示さなくてはならないのです。
このような場合にネームプレートはとても便利です。
一度作ったら年度末まで使えるネームプレートを活用し、みんなの自己存在感を高める工夫をしていきましょう。
子どもたち一人一人とお話しよう
学校アンケートやいじめアンケートなど、子どもたちにアンケートをとることがあります。
その際、「悩みや困っていることがあれば書きましょう」という欄があり、子どもたちは自由に記述できるようになっています。
しかし、自己存在感が低く、困っている子どもたちは「悩みがある」などと書いてくるはずがありません。
なので、初めから全員との「お話タイム」を設けておきましょう。

休み時間と放課後は名簿順で呼ぶから1人ずつ先生のところに来てね〜!
クラスの子どもたち一人一人が「先生と2人で話して自分のことを気にかけてくれた」と思えることは、子どもたちの「自己存在感」を高めることにつながります。
心の第2担任制度を取り入れてみよう
子どもたちは多かれ少なかれ、「先生を独占したい」「先生と二人きりでかまって欲しい」という願いを抱えています。
本書では、先述した「一人一人とのお話タイム」に似ていますが、「心の第2担任制度」が提案されています。
「心の第2担任制度」とは、「自分の話を聞いてほしいと思う先生を2〜3人選び、その中の一人と10分程度話をする」というものです。
また、「選ばれた教師は普段から気をつけて見たり、積極的に声をかけたりする」ということも行なっていきます。
つい、担任との一対一対応になりがちな学校現場を他の教員との結びつきも強くしていくことで、子どもたちの「自己存在感」を高めることができます。
異年齢での活動をどんどん取り入れよう
遊びや学習、掃除や登下校など毎日の生活の中に「異年齢での活動」をどんどん取り入れることも「自己存在感」を高めることにつながります。
- 甘え欲求の強い低学年は高学年を一緒にいることで心が満たされる
- 高学年は低学年に頼られることでしっかりとしてきて、自分の成長を実感したり、存在感を感じられる
「異年齢活動」はどの学年の子にも「自己存在感」を高める機会になります。
ぜひ、積極的に取り入れてみましょう。

共感的な人間関係を形成する
現在、子どもたちの「コミュニケーション能力の低下」が大きな問題となっています。
不登校、いじめ、非行など子どもの問題行動の背景に共通しているのが「自己存在感の低さ」と「人間関係能力の低さ」だと言われています。
子どもの問題行動を減らし、「自己指導能力」を高めるための方法の2つ目は「共感的な人間関係の形成」です。
本書では、「共感的な人間関係の形成」の基盤は「学級経営」にあると言われています。
目指すべき学級経営、理想の学級とは「秩序とふれあいのある学級」です。
具体的にいうと以下のような学級を目指します。
- 学級内にルールが定着し、侵害される心配がない
- ここにいて安心できると思える
- お互いを認め合える雰囲気がある
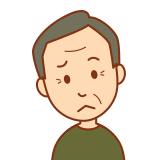
では、どうすればそのような学級、人間関係が作れるの?
小集団を活用しよう
ずばり、「小集団の活用」です。
ペアやグループ、班などの小集団を作り活動の場を仕組みましょう。
そこで、「他の子との心のふれあいを体験すること」で共感的な人間関係を形成していくことができます。
「構成的グループエンカウンター」と言われている活動も同様です。
構成的グループエンカウンターとは,リーダーの指示した課題をグループで行い、そのときの気持ちを率直に語り合うこと「心と心のキャッチボール」を通して、徐々にエンカウンター体験を深めていくものです。
構成的グループエンカウンター「図書文化」より引用
- みんながんばっているんだ
- 悩みはそれぞれ持っているんだ
- 協力してがんばったら前向きになれたぞ
- みんな僕のことを認めてくれている
そのような心の交流を積み重ねることで「共感的な人間関係」は形成されていきます。
異年齢での取組を活用しよう
「自己存在感を与える」にも具体例としてあげた「異年齢での取組」は「共感的な人間関係の形成」においても効果を発揮します。
- 低学年は高学年を頼れる上級生として慕い、信頼できる
- 高学年は低学年に頼られることで、大切に思い、接する
教室内だけでは体験できない「人間関係」を教師が仕組むことで「共感的な人間関係」は築いて行くことができます。

自己決定の場を与える
「自己指導能力」を高めるための方法の3つ目は「自己決定の場を与える」ことです。
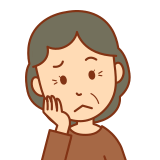
子どもたちはいつも自分で考えたり、発表したりしてしているけどそれとは違うの?
子どもたちが普段見せている行動は「子どもたち自身によって自己決定されたもの」でしょうか。
教師が説く「あるべき姿」を先取りして、自分から進んで「教師の望むいい子」になってはいないでしょうか。
ここでいう「自己決定」とは以下のように定義されています。
このように自己決定するための情報を提供し、自己決定の場を様々なシーンで与えることが大切です。
学校行事で自己決定させよう
まず、あげられるのが「学校行事での自己決定」です。
本書で例としてあげられていたのは「修学旅行」です。
決められたコース、決められた行程をただ旅行するだけの修学旅行で子どもたちの「自己指導能力」を育むことはできません。
- コースを自分たちで決める
- 行く場所を自分たちで決める
- 休憩時間の取り方も自分たちで決める
教師が決めたことに従わせるだけなら、管理もしやすく、教師の目も行き届き、指導自体は楽になるでしょう。
子どもたちに自己決定させるためには、「あらゆる場面」「あらゆるシーン」を想像し、教師が手立てを打っておくことが必要になります。
指導の負担が一気に増えてしまうことは目に見えています。
しかし、だからこそ子どもたちが「自己決定」することで「自己指導能力」を高めることにつながるのです。
各教科で自己決定させよう
「自己決定の場」は大きな学校行事だけで準備するものではありません。
むしろ、日々の授業の中でこそ「自己決定の場」を意識して与えていくことが大切です。

学校行事に比べ、授業の時間数は圧倒的に多いからね!
知識や解き方を一方的に教え込む、一斉指導では「自己決定の場」を与えることはできません。
与えられた知識、解き方を使いながら、自分で問題解決の方法を探り、試行錯誤できる授業づくりが必要です。
まさに、「主体的・対話的で深い学び」の実現こそが、「自己指導能力」をつけることにつながることを実感しますね。
- 答えではなく、解き方を考える
- 選択肢の中から正しいと思うものを選ぶ
- 答えのない問いにも、自分の立場を明確にする
教師の授業改善で子どもたちの「自己指導能力」は高められます。

【まとめ】生徒指導の3機能を生かして自己指導能力を高めよう!
生徒指導の究極の目標「自己指導能力を高める」を目指し、生徒指導の3つの方法の具体例を紹介してきました。
「生徒指導の3機能」と言われるとなんだか難しそうですが、それぞれ1つずつ細かくみていけば、明日からの実践にいかせそうなものが1つだけでも見つかったのではないでしょうか。
何より、教育で大事なのは「子どもたちが自分の人生をより幸せに生きていける力」をつけることです。
そのための「生徒指導」であり、そのための「自己指導能力」であり、そのための「生徒指導の3つの機能」です。
木を見て森を見ずにならないよう、大きな目標をいつも見失わずに共に、実践を積み重ねていきましょう。
本書には、まだまだ「生徒指導」についての知識や実践例が収められています。
気になる方はぜひ、チェックしてみてください。
それではまたっ!
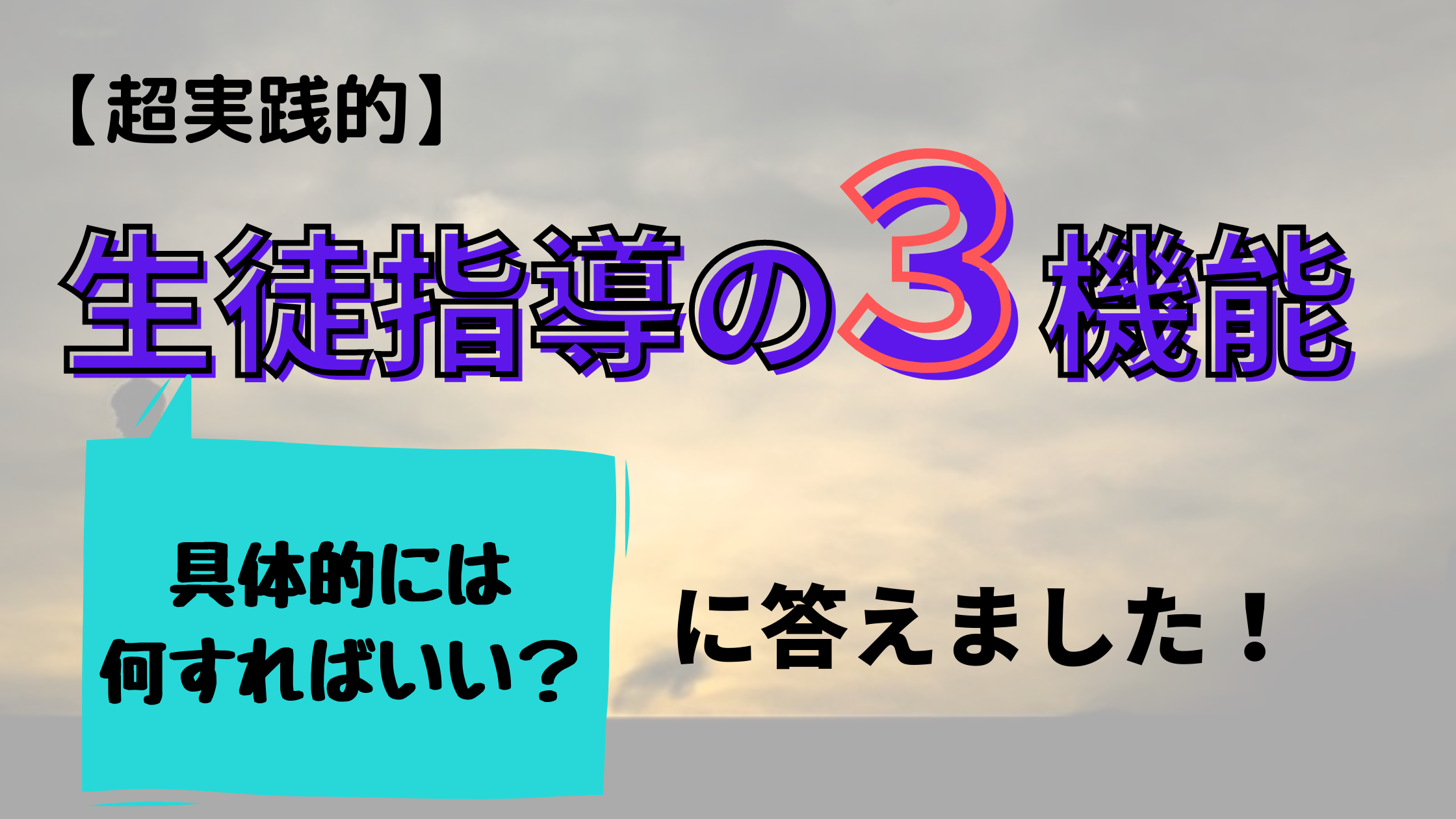
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e6a5c41.fbe701de.1e6a5c42.e1d34898/?me_id=1262790&item_id=10990572&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fguruguru-ds%2Fcabinet%2Fb%2F6%2F305%2F9784810036305.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

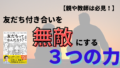

コメント