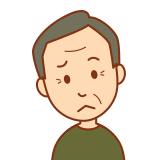
学級経営に力を入れたいんだけど、何をすればいいのか…
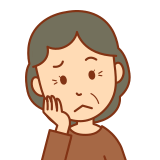
若い先生にアドバイスしたいんだけど、なんて言っていいのか…
学級経営に苦戦し、毎日仕事に行くのが「辛い」と悩んでいる若手の先生がとてもたくさんいます。
実際に私の学校にも、「学級崩壊」という言葉が現実味を帯びてきてしまっている先生が2人います。
そんな先生になんと声をかけていいのか…といつも悩んでしまいます。
でも、「時すでに遅し」の可能性がかなり高いんですよね。
今日は、誰もが恐れる「学級崩壊」を未然に防ぐためのたった1つのポイントを解説します。
私が10年以上、学校現場で働いてきた中で得た「1つの教訓」です。

【そもそも学級崩壊とは】
文部科学省のホームページでは、「学級崩壊」を以下のように定義しています。
「子どもたちが教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しないなど、集団教育という学校の機能が成立しない学級の状態が一定期間継続し、学級担任による通常の方法では問題解決ができない状態に立ち至っている場合」を「学級がうまく機能しない状況」と捉える
文部科学省ホームページより
・教師の指示に従わない
・授業が成立しない
・集団教育が成立しない
これらの「子どもの崩壊」に加え、忘れてはならないのが「教師の心の崩壊」です。
【学級崩壊の忘れてはならない一側面】
ボクはこの「教師の心の崩壊」こそが「学級崩壊」だと感じています。
むしろ、
とさえ思っています。
でも、現実は学級がしんどくなってくると、必ず先生の心も崩壊への道を進み始めます。
【勤務校の若い先生の一例】
ボクが勤務している小学校の若い先生は日に日に以下のような姿を見せるようになってきました。
・出勤時間が遅くなってくる
・ため息をついている
・「教室に行きたくない」と言う
・涙することがある
これは、完全に「教師の心の崩壊」の一例です。
【学級崩壊を未然に防ぐためのたった1つのポイント】
では、実際に「学級崩壊」を防ぐために必要なことはなんなのか。
これは100人に聞いたら100通りの答えが返ってくるところです。
・授業力
・生徒指導力
・子どもを理解する力
どれも様々な研修や書籍で言われていることですが、どれも曖昧で漠然としすぎています。
そして、誰にでもできるものではありません。
ここでは、「誰もが意識すればできる」ことをお伝えします。
それは、
ということ。
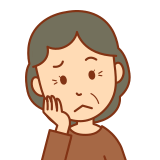
「◯◯の前を制する」とはどういうこと??

【「◯◯の前を制する」ことで学級崩壊は防げる】
「◯◯の前を制する」とは、「子どもが◯◯をする前に教師がその雰囲気を作っておく」ということです。
これを意識することで「子どもの雰囲気に教師が対応する」のではなく、「教師の作った雰囲気の中で子どもたちに活動させる」ことができるようになります。
これができるかできないかの差が、「学級崩壊」への道を進むか進まないかの大きな違いとなります。
それでは、「◯◯の前」を具体的に解説します。
①子どもの登校前に学級を制する
子どもが登校してくる時間には教室に入り、子ども達を待ち受けられるようにしましょう。
教室に入ってきた子ども達に対して「〜〜君おはよう!」「〜〜さんおはようございます!」と元気に声をかけます。
これだけで、「教師が朝の空気」を作り出すことができます。
子ども達がガチャガチャしている教室に後から入り、「みんなおはよう〜!」と声をかける。
これは「子どもの雰囲気に教師が合わせているだけ」になってしまいます。
「〜〜君、昨日もサッカー頑張ってたね!」
「〜〜さん、髪の毛切った?いい感じ〜!」
などとプラス一言が付け加えられたら、朝の教室の空気を支配することはバッチリです。

②始業開始までに手元の仕事を終え、自分の心に余裕を与える
朝、子どもたちの登校を教室で待ち受けられたら、すぐに宿題の◯付けを始めましょう。
基本は始業までに「全ての◯付けを終える」ことです。
「〜〜さん、今までよりさらに丁寧な字が書けてるね!」などと一言付け加えながら◯付けできると最高です。
始業までに◯付けが全て終えられていると、その後の仕事が一気に余裕を持って取り組めます。
休み時間も子どもと遊んだり、話をしたり。
それらの積み重ねが「学級崩壊」を防ぐことにつながります。
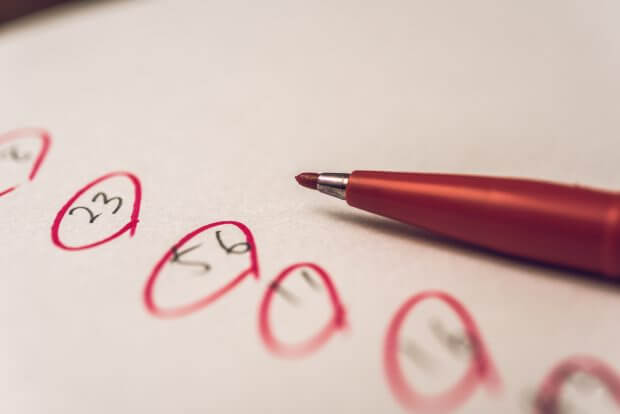
③授業が始まる前の空気を制する
授業が始まる1分前には、教室の前に立ち子どもたちに声かけをし始めましょう。
「そろそろ始まるぞ〜!」
「次は社会!教科書ノートは出てるかな?」
授業前から声かけを始めることで、授業のスタート時に空気を支配することができます。
そうすれば、スムーズな授業の開始を迎えられます。
・チャイムがなっているのに、教師はいない。
・子どもたちはチャイムを無視し、ウロつく
・後からきた教師が「早く座りなさい!」と焦って注意する
・子どもがしぶしぶ動く
これでは、学級崩壊への道に一直線です。
授業開始前の空気を支配しましょう。

④給食前の学級の雰囲気を制する
子ども達がばたつき始めるのは、給食時間です。
授業が終わり、多少心が解放されるのは仕方ありません。
でも、その時間に教師も一緒になってゆっくりしていてはいけません。
教師もすぐにエプロンを着て、「さっ、給食取りに行くぞ!早く並ぶ!!」と給食当番を引き連れて動きましょう。
もちろん、配膳を待っている子ども達への声かけも忘れないようにしましょう。

「待っている人は、静かに読書ね!じゃあ、給食当番、出発!!」
そう言って教室を後にすることで、給食前の教室の空気を作り出すことができます。

以上、学級崩壊の未然防止に向けた「◯◯の前を制する」ための4つのポイントでした。
【学級崩壊を防ぐために「◯◯の前を制する」まとめ】
①子どもの登校前に学級を制する
②始業開始までに手元の仕事を終え、自分の心に余裕を与える
③授業が始まる前の空気を制する
④給食前の学級の雰囲気を制する
以前、学級経営について『策略 ブラック学級づくり』(明治図書)から学んだポイントをまとめた記事は以下のものです。
合わせてご覧ください!
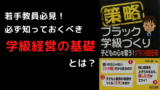
これらのポイントを意識することで、グッと学級経営の力が高まるはずです。
あなたの教師としての毎日が、今より一歩幸せなものになりますように。
それではまたっ!
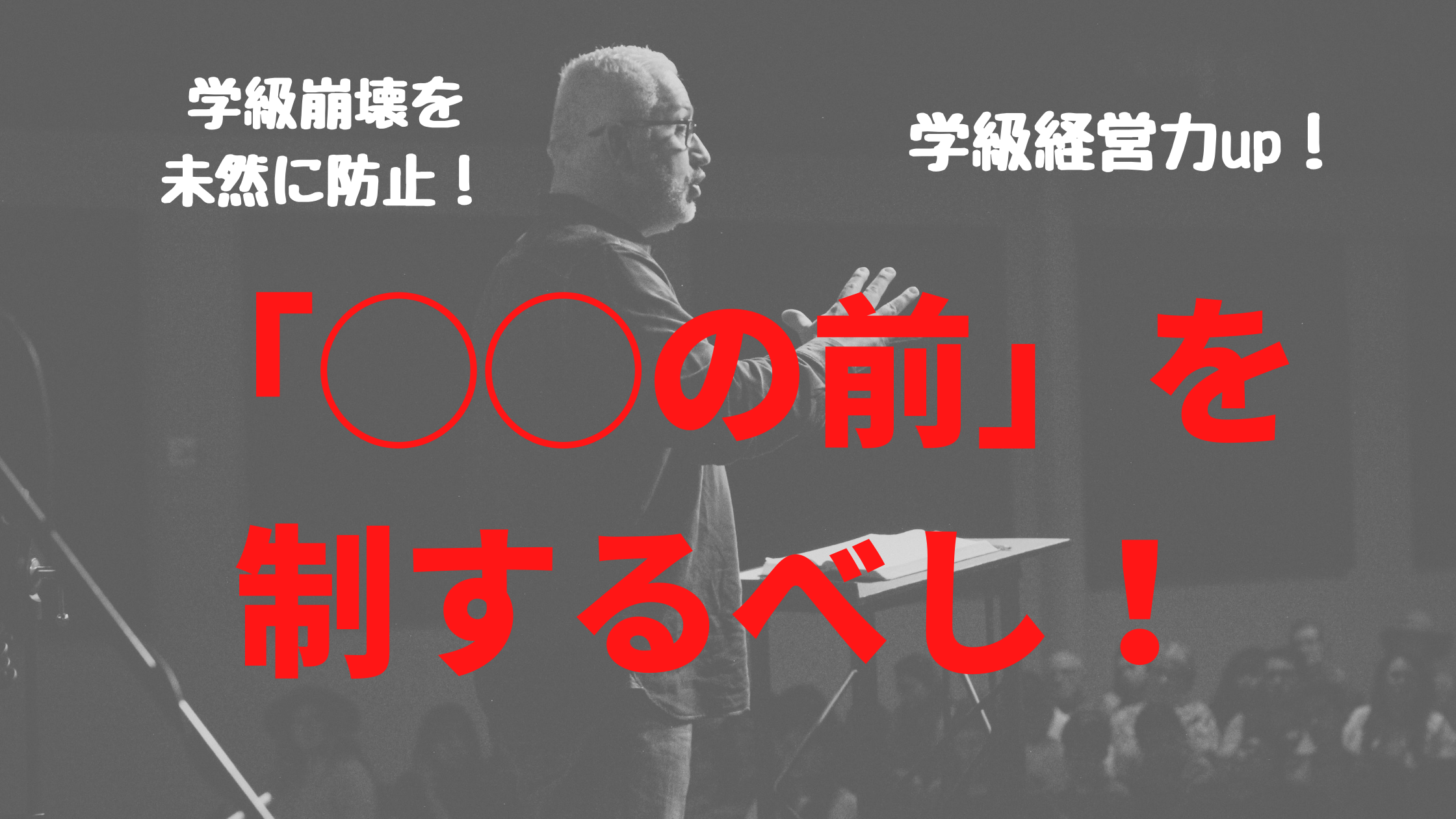
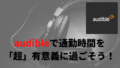

コメント