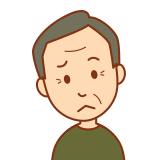
Twitterで「#先生死ぬかも」が話題になってたね
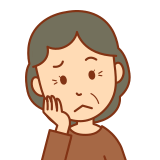
「死ぬかも」と思うほど学校はブラックなのかもしれないわ
学校現場や先生たちの仕事が「ブラック」だと言われて久しいです。
そして、最近はTwitterで「#先生死ぬかも」というワードが話題になりました。
10年間小学校で勤務し、学校現場のリアルを見てきたボクは「学校現場がブラック」な理由は「たった1つ」だと考えています。
まずは結論から!

学校現場がブラックなのは先生が「自己決定する機会」がなさすぎるから!
今回は、
・ボクがそう断言する理由
・「先生の自己決定」とはどういうことか?
・どうすれば、学校で幸せに生きていけるのか?
についてボクなりにまとめてみます。

【学校が「ブラック」なのは先生が「自己決定」する機会が無いから】
・子どもが好き
・子どもと楽しく生活したい
・子どもの成長に携わりたい
そう夢や希望を持って先生になる人が多い学校現場。
そんな学校現場がここまで「ブラック」になっている理由は「先生の自己決定する機会」が少なすぎるからだと考えています。
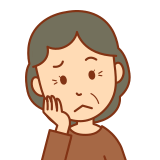
でもそれだけ言われてもどうすればいいか分からないわ…
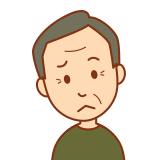
「自己決定する機会」ってどういうこと?
【「自己決定」とはどういうことか】
その前に、まず「自己決定」とはどういうことかをおさらいしましょう。
といっても、読んで字のごとくですが、「自分で何かを決める」ということですよね。
あなたは、普段の生活で「自己決定」していますよね?
・今日はこの服を着よう!
・朝ごはんは◯◯を食べよう!
・この休みは買い物をしよう!
・今年の夏は△△に行こう!
この、「自分の行動を自分で決める」という行為を「自己決定」と言います。
ここで大事なのは「自分で決める」ということです。
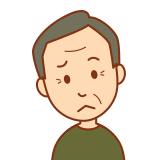
なぜ「自分」で決めることが大切なの?
なぜなら、「自分で自分の行動を決める」ことで「幸せ」になれるからです。
メンタリストDaiGoさんのYouTubeではこのようなことが指摘されていました。
さまざまな研究によると、自分の人生を自分の力でコントロールできているという実感がある人は、そうでない人に比べて幸福度が高いし、幸せだし、仕事のモチベーションが上がるということがわかっている。
https://www.youtube.com/watch?v=sUMABLNySY8

【学校現場で働く先生の現実は】
では、学校で働く先生たちはどれくらい「自己決定」ができているかというと…。
先生たちの自己決定できる機会は皆無に近い
と言ってもいいでしょう。
そして、これがどんな結果をもたらすかと言うと、
先生たちは幸せにはなれない
ということです。
そして、最終的には
・先生やめたい
・「#先生死ぬかも」
ということで、今の学校社会、学校現場が完成しているということになっているわけです。

【「自己決定」が圧倒的に欠けている学校現場の仕事】
・授業をする
先生の仕事の基本は「授業をし、子どもに学力を付ける」ということですよね。
しかし、この「授業をする」という仕事自体も
・指導要領で決められた内容を
・決められた教科書を使って
・決められた実施時期に
・決められた内容を指導し
・決められた評価項目での評価をする
という状態です。
先生たちが「自己決定」できることは、「この1時間をどう授業するか」という最後の最後の部分だけです。
しかし、これもあくまでも「指導書」という先生用の教科書を少しだけアレンジするという程度にすぎません。
内容や方法に縛られず、オリジナルの教材などを使って授業をすると注意を受けてしまいます。
「自己決定している」といえる状態とは程遠いと言っていい状態です。

・職員会議や校内研修
職員会議や校内研修というものが、子どもの下校後や長期休みに数多く設定されています。
・紙を見れば分かるはずの資料を延々と読むだけの時間
・決まった人が意見を言うだけの時間
・決められた内容を聞くだけの時間
そんな会議や研修があまりにも多い現状です。
会議中に「自分で考えて行動・発言する」という機会は若手教師には「ない」と言っていいでしょう。
ここにも「自己決定」はありません。

・学校行事に取り組む
普段の授業以外に「学校行事」があります。
・運動会
・学芸会
・遠足
・宿泊学習
それらの「学校行事」は、一応「職員会議を経て決められた」とされていますが、「今まで通り」に進められることも多いです。
一人一人が「自己決定」し、やるかやらないかを考えたり、意見を言ったり、内容を変えたりすることはほとんどありません。
先生の自己決定はここにもあるとは言えません。

・出張
先生たちはよく出張に行くことがあります。
でも、その出張も
・決められた出張に行く
・毎年、同じような内容の話を聞く
・決められた書類にまとめを書いて提出する
なかなか「自己決定する機会」はないと言っていいでしょう。

・保護者対応
近年、学校現場の仕事の負担が一気に増えている原因にこの「保護者対応」があります。
「モンスターペアレント」という言葉もできましたが、これらも「保護者の対応に学校がゆらぐ状態」のことを指しています。
・保護者の思いにこたえる
・保護者が連絡してきた時間に対応する
・保護者の都合に合わせる
・保護者の話を聞く
学校、先生は常に「保護者に合わせる」というスタンスをとり続けざるをえません。
さらに最近は「学校の問題」と「家庭の問題」の境界がわかりづらくなっているようにも感じます。
保護者対応については「受け身」になっていることが数多く、自己決定は皆無と言っていいでしょう。

・今までになかった新しい取組
さらに学校現場には、国や都道府県、教育委員会から多くの新たな取組がおりてきます。
・キャリアパスポート
・土曜日を活用した授業
・プログラミング教育
・外国語や道徳の教科化
学校現場の思いや現状とはあまりにも乖離した取組や内容がどんどん増えています。
現状と「やるべきこと」のバランスが崩れてしまっているとボク自身は感じています。
さらに、それらの仕事は「やらないといけない仕事」であり、完全に「自己決定の機会はない」ものになってしまっています。

・そして疲弊した先生が子どもに接すると…
今まで上げてきたように「自己決定」の機会が少なく、「させられる仕事」ばかりをしている毎日。
多くの先生たちは体力的にも精神的にもかなり疲弊しています。
そんな先生が子どもたちに接しています。
・ゆっくり話を聞く余裕がない
・すぐに解決しようとしてしまう
・イライラしてしまう
最終的には「先生たちの自己決定のなさ」が「子どもたちへの教育の質の低下」につながっている現状があると考えています。

【「#先生幸せかも」で生きるために】
では、今の学校現場をどうすれば明るく、幸せに生きていけるのか。
それは「自己決定」する機会をいかにたくさん作れるかということにかかってきます。
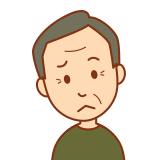
でも自己決定しなければ、無難に生きられそうだよね…
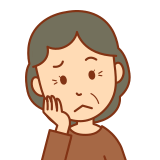
言われたことをやっておくだけの方が楽な気がするわ…

失敗を恐れず「自己決定」することでしか幸せになれないよ!
当然、「自分で考えて行動」するわけですから、失敗がともないます。
言われたことをやっておくだけの方が楽ですからね…。
でも、そうやってみんなが生きてきた学校現場の過去が今の学校を形作っているわけです。
今、一人一人が「自己決定」をして、学校現場を「幸せ」に変えていきましょう!
・授業で自己決定を
何と言っても、子どもたちが長い時間を過ごす「授業」の時間を楽しいもの、有意義なものに変えたいですね。
今までのように「指導書の枠に収まった授業」から一歩、外に踏み出してみてはいかがでしょうか。
・これ、めっちゃおもしろそうじゃん!
・こんなのできたら楽しそう!
・これなら自分も受けてみたいな!
そんな風に、自分の感動を大事にして授業をしてみましょう。
「やらないといけない授業」が多い中、1週間に1時間だけでも「やってみたい授業」をしてみましょう。
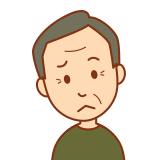
そんな授業ってどうやって調べるの?
・民間の研究会に行ってみる
・書籍で探す
・インターネットで探す
いろんな方法を使い、学校や指導書・教科書の外から「楽しそう!」という授業を探し、それを実践してみることをオススメします!
そこには先生自身の「自己決定」があり、その先に先生たちの幸せがあるはずです。
ボク自身が参考にしている書籍を以下に紹介します。
「子どもたちが楽しんでくれる授業」「先生自身が楽しい授業」が数多く紹介されています。

・自己決定の機会を自ら作り出そう
冒頭で紹介したDaiGoさんの言葉を改めて紹介します。
さまざまな研究によると、自分の人生を自分の力でコントロールできているという実感がある人は、そうでない人に比べて幸福度が高いし、幸せだし、仕事のモチベーションが上がるということがわかっている。
https://www.youtube.com/watch?v=sUMABLNySY8
先ほど紹介した「授業」以外にも、先生自身が「自己決定」して行動できるチャンスは他にもありそうです。
・自分自身が「自己決定」できるのはいつか?
・自分が責任を持って行動できる機会はいつか?
日々、そう考えながら行動することが「自分自身の幸せ」につながります。
今日から一歩、行動してみましょう!
それではまたっ!

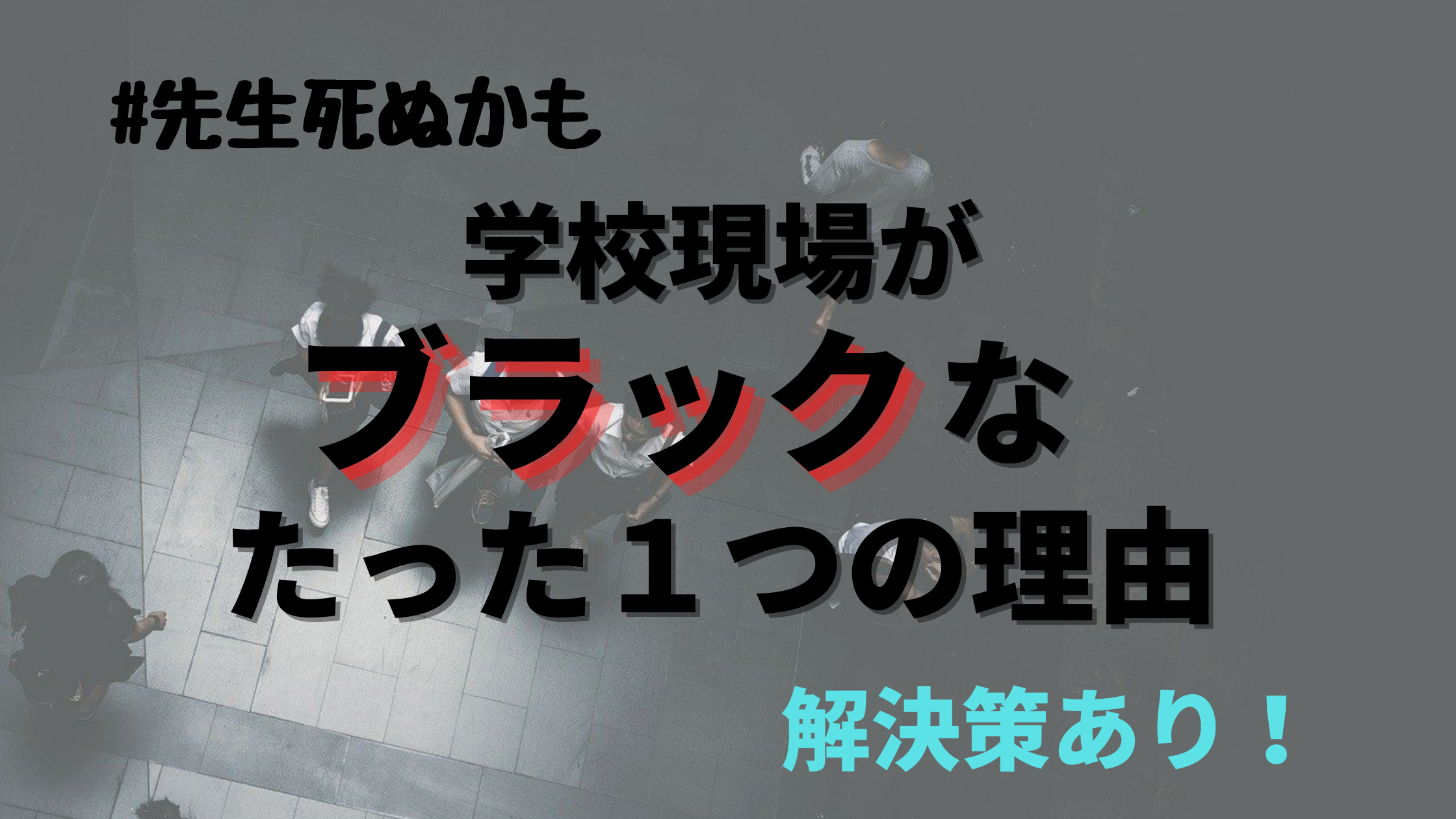
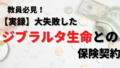

コメント